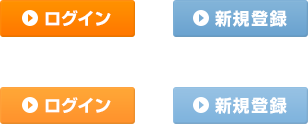![]() 2018年12月1日(土)19:00
2018年12月1日(土)19:00
【氷川教授の「アニメに歴史あり」】第10回 セル画に見た「アニメのホンモノ」
11月17日から三鷹の森ジブリ美術館の企画展示「映画を塗る仕事」がスタートした。これは故・高畑勲監督と宮崎駿監督の「色へのこだわり」を具体化した色彩設計の故・保田道世さんによる「仕上げ」の仕事を中心に紹介するものだ。内覧会で拝見したとき、やはり絵の具時代の「セル」には独特の価値が宿っているぞという感慨を新たにできた。
展示の中でも1971年ごろに両監督が「セル上の色で何が表現できるのか」で参考としたロシアの絵本作家であるイワン・ヤコヴレーヴィッチ・ピリービンの挿絵は非常に見ごたえがあった。森の中で手前奥に密生している木々に対し、個々の樹木は平面的に描かれているのに、彩度を低くした緑色をいくつも使い分けることで、夕暮れ時の表現としていたりする。特徴的な「水の塗り分け表現」など、宮崎アニメを通じて広く日本のスタンダードとなった様式のルーツが明確化されていて、刺激的であった。
会場ではこの発想を日本的に膨らました仕上げのテクニックについて、「光を塗る」などの表現で「色変え」の展示に大きなスペースを取っていて、非常に感銘を受けた。大学院におけるアニメ技法の講義では、そもそもの話として「絵の具を塗るから色が発生する」のではなく「光源が被写体に当たった反射光を空気と眼球のレンズを通して網膜にあたったものを色と認識する。それを絵の具で表現している」ということから教えている。
朝と昼と夕方と夜など、時刻によって光源が変化すれば反射光も変わるし、明暗のバランスも違ってくる。自然光(太陽光)6000ケルビンの色温度で設計された「ノーマル色」を、心理や映画全体の位置づけを考慮し、背景とのマッチングを重視して色を変えていく。その変え方を絵の具の選択の中から行うところに、芸術的な美意識が宿る。映画の印象が1コマずつ作画の積みかさねのトータルで決まるのと同じくらい、カットカットでバランス調整した色の積みかさねで、物語中の感情の残り方も決まるのである。
さて何より嬉しいのは、これを「セル画」という「物体」で示したことだった。セル絵の具は彩度が高めで、透明板の裏から塗ることで、書籍のコーティングと同様に明解な押し出しが出る。そして誰が見ても「この色」と分かる「ホンモノ」がそこにあるという動かぬ事実――そこに改めて感銘を受けた。もちろん現在のデジタル制作でもマスモニ(マスターモニター)で調整した色の「ホンモノ」はあるが、デジタルゆえに再生環境や印刷状態で簡単に色が変わる(「色が転ぶ」という)。最大公約数的に「この色」とされているだけで、セル画のように一義に決められる「ホンモノ」は存在しないのである。
と、そこまで考えたとき、その「ホンモノ感」が自分のアニメへの深い関心の原点であることを思い出した。その「ホンモノの希求」は、1974年の11月、放送開始して間もない「宇宙戦艦ヤマト」の見学と称して、練馬区桜台にあったオフィスアカデミーのスタジオを訪ねた動機なのである。簡単に言えば「セル画」が欲しかった。それはマニア的なアイテムとして欲しいというより、むしろ「ホンモノの色」が知りたかったのが動機の根本にあった。たとえば当時発売された「ヤマトのプラモデル」は水色だったが、テレビを見ても雑誌を見ても、もっと暗くて濃い色をしている。であれば塗り直さなければならない。さて、それでは何に合わせるべきか。それは「セル画」という「ホンモノ」がある以上、他にはない……という発想なのだ。
なぜ「セルがホンモノ」と思ったか? それはその数年前、「アタックNo.1」のセル画を見て衝撃を受けたことに端を発する。瞳の色がブルーやグリーンに塗られていて、テレビを見て気付かなかったので愕然とした。「日本人の瞳だから」と脳内で塗り直して認識していたことになる。だが「作り手」は違うふうに「塗っている(設計している)」という意図が、それで発覚したのだった。
ということは「ヤマト」だって……と、そんな軽々しい気持ちで行ったが、実際にセル画はなかなか入手できなかった。一方で、主にチーフディレクターの石黒昇さんに接近して談話を聞き出すと、絵の具の話の奥深さが判明していき、それで別種の刺激が発生したのである。たとえば第4話を境に絵の具会社を抜本から変えているので、色が全体に違っているという。「ヤマト色」という特色があって上半分はZ-4、下半分の赤いところはZR-4など特別な番号体系となっていること。パイロット版では、セルの反射を恐れてヤマト色の明るい方を使っていたこと(プラモが水色をしている原因も判明した)。西崎義展プロデューサーの指示で「ヤマトの色を暗くしろ」と言われたので、放送中から暗くなっていたりすること……。
そういう話を聞くまでは「ヤマトは全部同じ色に塗られてるはずだから、セルをひとつ確かめればホンモノの色が分かる」と思いこんでいた。ところが「色は決めるもの、作りこんでいくもの」という「ものづくりの発想」が浮き彫りになっていって、そこにいたく感激したのであった。それは同時に「自分の見た目を過信しない」という「研究への第一歩」につながる触発を内包していたのだと、今になって思いあたった……。
今回の美術館展示で何よりもサイコーだと思ったのは「映画を塗る仕事」という題名である。そこには「塗る」という「意志」が見える。同時に「塗った人」という主体も感じとれる。アニメの現場に「セルというホンモノ」がなくなったいま、もしかしたらこの企画展で40数年前、高校生時代の筆者のような開眼的な体験をする若者が出たりしないか……などと、密かな願いが生まれる嬉しい場なのであった。

氷川竜介の「アニメに歴史あり」
[筆者紹介]
氷川 竜介(ヒカワ リュウスケ) 1958年生まれ。アニメ・特撮研究家。アニメ専門月刊誌創刊前年にデビューして41年。東京工業大学を卒業後、電機系メーカーで通信装置のエンジニアを経て文筆専業に。メディア芸術祭、毎日映画コンクールなどのアニメーション部門で審査委員を歴任。
イベント情報・チケット情報
- 「映画を塗る仕事」展
-
- 場所
- 三鷹の森ジブリ美術館(東京都)
特集コラム・注目情報
関連記事
イベント情報・チケット情報
- 2018年8月28日(火)
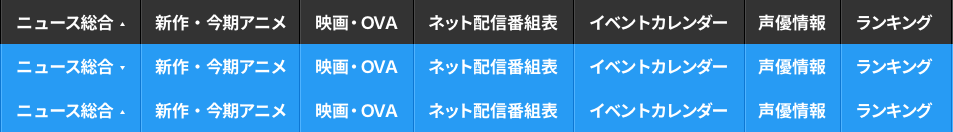








![劇場上映版「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」Blu-ray...[Blu-ray/ブルーレイ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ejpY40zbL._SL160_.jpg)
![さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち 4Kリマスター(4K ...[Ultra HD Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41xyJFHqWNL._SL160_.jpg)
![宇宙戦艦ヤマト2199 Blu-ray BOX【特装限定版】[Blu-ray/ブルーレイ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41Vgr7OhnpL._SL160_.jpg)
![劇場上映版「宇宙戦艦ヤマト2199」Blu-ray BOX(特装...[Blu-ray/ブルーレイ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51iv6wQTN7L._SL160_.jpg)
![宇宙戦艦ヤマト 劇場版 4Kリマスター(4K ULTRA ...[Ultra HD Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41ScDSAAxrL._SL160_.jpg)