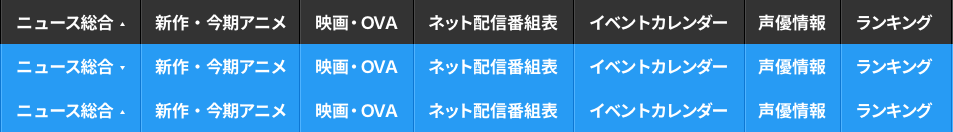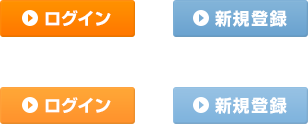![]() 2022年6月11日(土)19:00
2022年6月11日(土)19:00
【編集Gのサブカル本棚】第15回 「原作通り」の歩き方

イメージを拡大
アニメ化もされた久米田康治氏の漫画「さよなら絶望先生」に「原作通り」というネタがある。原作のある映画がつまらないと叩かれている監督が、「原作通りだから!」と言い訳しながら「原作通り」という名前の路地に逃げこむというものだ。センシティブなところを突いていく「絶望先生」らしいエピソードで、「原作通りから大きくはずれると大批判を浴びる事が多いのです!」という発言もでてくる。そうしたネタになるぐらい、原作物の映像化が原作にどれぐらい忠実であるかを作り手も受け手も気にするようになってきた。
劇場アニメやテレビアニメの分野で筆者が見てきた範囲で言うと、原作に忠実と言われるかどうかは尺の問題が大きいように思う。劇場アニメであれば2時間前後、テレビアニメであれば1話30分×1クールないし数クールという限られた時間で、原作のどこまでを描くのか。酷評される作品の多くはその配分に無理があって、原作のストーリーを極度に圧縮したり飛ばしたりして、原作ファンにも未読者にもうれしくないものになりがちだ。そこで脚本家が槍玉にあげられることが多いが、そうした大枠の部分はプロデュースサイドで決定されているはずで、脚本家ばかりが責められてしまうのは気の毒だなと思ってしまう。
メディアの違いを理解せよ
「原作通り」のど真ん中をいく方法として、原作者自らがシリーズ構成や脚本に携わるケースもある。原作者がやっているのだから原作と違うとは言わせない――となってしかるべきだが、残念ながら毎回そう上手くはいかない。原作者こそ原作通りにやることに飽きていることもあるし、「餅屋は餅屋」という言葉の通り、優れた原作者が必ずしも自分のフィールドと異なるメディア化を巧みにコントロールできるわけではないからだ。
ライトノベルが原作のギャグアニメ「生徒会の一存」の1話冒頭では主要キャラクターがアニメ化緊急会議を行う様子がパロディ満載で描かれ、主人公が「メディアの違いを理解せよ!」と高らかに宣言する。「アニメはアニメなりの見せ方をしたほうがいい」「それって原作クラッシャー……」といったやりとりもあり、ギャグのオブラートに包みながらも、原作物を手がけるアニメスタッフの苦悩や本音が見え隠れしているように感じた。
脚本家・橋本忍氏の回想
そもそも原作に忠実な映像化は存在しうるのだろうか。よく言われることだが、原作を映像化する行為は批評であり、作り手が原作をどう捉えているかを表現したものだという考え方もある。読者が思い浮かべたそれぞれの原作像があるなかで、作り手はその最大公約数を探りながらも、作っていくなかで自身の思いが自然と作品にのってしまうという話をよく聞く。また、原作に忠実なアニメ化だと評判の作品を原作とよく見比べてみると実はそんなことはなく、映像化にあたって絶妙なアレンジやオリジナル要素が加えられていることも多い。
映像化されるほどの原作には、漫画や小説などそのメディアでしか表現できない要素があるはずで、限られた尺でそれを描くには映像化の指針になるような何かが必要になる。そのことに関する名文として、「モテキ」「バクマン」などの漫画原作を見事に実写映画化した大根仁監督はブログで、橋本忍氏による自伝「複眼の映像」を紹介したことがあった。
橋本氏は「羅生門」「七人の侍」など黒澤明作品の共同脚本を手がけた脚本家で、前掲書では橋本氏が駆け出しだった1946年、亡くなる直前の伊丹万作監督(伊丹十三監督の父)から原作物の脚本を手がけるときの心構えについて問われたことを回想している。橋本氏は原作を牛にたとえ、綿密に観察して急所が分かると一撃で殺し、「流れ出す血をバケツに受け、それを持って帰り、仕事をするんです」と話し、「原作の姿や形はどうでもいい。欲しいのは生き血だけなんです」と伊丹監督に答えている。伊丹監督はその答えを受けとめつつ、「この世には殺したりはせず、一緒に心中しなければいけない原作もあるんだよ」と返したと橋本氏はつづっている。このエピソードをブログで紹介した大根監督は自身が手がけた原作物の仕事で、「上手くいったものは間違いなく『一撃で殺せた』ものであり、上手くいかなかったのは『殺し損ねた』ものだ」と振り返っている(編注1)。
あるアニメ化作品の原作者に取材したとき、キャラクターさえブレずにやってもらえればそれ以外は変えても構わないと聞いて、なるほどと思ったことがある。橋本氏の「欲しいのは生き血だけ」に通じる考え方で、アニメ化で「〇〇はそんなこと言わない」と原作ファンに思われてしまうのはたしかによくない。毎年新作映画が公開されている「ドラえもん」などの国民的アニメが制作スタッフが異なっても地続き感があるのは、毎週放送されているテレビアニメによってキャラクターが確立されているからで、ブランクを挟みつつ展開されている「ルパン三世」もキャラクターに強烈な個性があるから、長い間ファンに愛されているのだと思う。
原作と心中した作品
伊丹監督の「一緒に心中しなければいけない原作」というと、近年では劇場アニメ「この世界の片隅に」が思い浮かぶ。関係者の執念で実現にこぎつけた経緯や、戦時中の呉市や広島市を徹底的に調べて描いた片渕須直監督の狂気にも似たこだわりは心中と呼ぶにふさわしい。同作のヒット後、作品成立を優先させるために泣く泣くカットしたパートを復活させた長尺版「この世界の(さらにいくつもの)片隅に」が3年かけて制作され、約40分の新作パートによって新作といっていいぐらい作品の印象が大きく変わったことにも驚かされた。
こうした原作と映像化の幸せな関係を見ると、どの作品もこうあってほしいと期待してしまうが、心中というだけあってなかなかできることではない。ヒットして心中から生還できているから良い話になっているのであって、公開前に関係者の方から興行収入の目標が10億円だと聞いたときには、失礼ながら「そんな夢みたいなことはおきないだろう」と思ってしまったのを覚えている(※同作の興行収入は27億円を突破した)(編注2)。
そんな究極の映像化のひとつであるアニメ「この世界の片隅に」ですら、原作ファンの方のなかには不満をもつ人もいるだろう。実際、熱心な原作ファンの知人からアニメ版を見るつもりはないと聞いてもったいないと思いつつも、原作が好きだからこそ、どんなに良い出来であっても映像化を見たくないというファンの心理もあるのだと納得させられた。(「大阪保険医雑誌」22年3月号掲載/一部改稿)
編注1:大根仁のページ「クワイエットルームへようこそ」(2007年12月17日)
編注2:筆者はアニメ「この世界の片隅に」のクラウドファンディングに参加するぐらい同作を応援していたことを付け加えておく。

編集Gのサブカル本棚
[筆者紹介]
五所 光太郎(ゴショ コウタロウ) 映画.com「アニメハック」編集部員。1975年生まれ、埼玉県出身。1990年代に太田出版やデータハウスなどから出版されたサブカル本が大好き。個人的に、SF作家・式貴士の研究サイト「虹星人」を運営しています。
作品情報

-
すずは、広島市江波で生まれた絵が得意な少女。昭和19(1944)年、20キロ離れた町・呉に嫁ぎ18歳で一家の主婦となったすずは、あらゆるものが欠乏していく中で、日々の食卓を作り出すために工夫を凝...
-

この世界の片隅に コミック (上)(中)(下)セット
¥2,139

-
![この世界の片隅に [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51tmPczHpwL._SL160_.jpg)
この世界の片隅に [DVD]
¥4,180 ¥3,138

-
![この世界の片隅に [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61H6QDOdBJL._SL160_.jpg)
この世界の片隅に [Blu-ray]
¥5,280 ¥3,964

-

この世界の片隅に (上) (アクションコミックス)
2008年01月12日¥713

特集コラム・注目情報
関連記事
イベント情報・チケット情報
- 2024年8月3日(土)
- 2024年1月6日(土)
- 2024年1月6日(土)
- 2024年1月3日(水)
- 2023年10月28日(土)