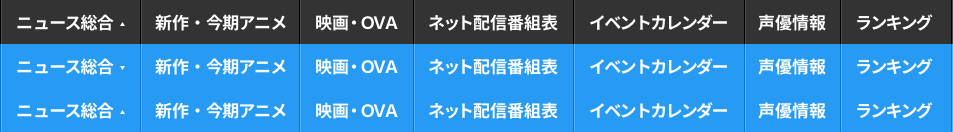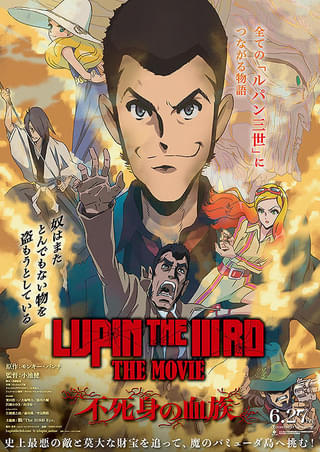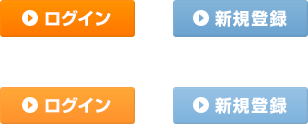![]() 2019年12月5日(木)20:00
2019年12月5日(木)20:00
【氷川教授の「アニメに歴史あり」】第22回 時間と空間がつくる“映画的世界”
片渕須直監督の映画「この世界の(さらにいくつもの)片隅に」が、いよいよ12月20日から公開される。今回、劇場用パンフレットや関連書籍類には、何も関与していない(主に氷川のスケジュールに起因する)。なのでこの場では形式張らず、前作に関して企画書からイベント、ビデオパッケージ用オーディオコメンタリーに参加してきた立場も交えつつ、思いつくまま感慨を記しておきたい。
この映画は、こうの史代の原作漫画をアニメーション映画化した「この世界の片隅に」(2016年11月12日公開)の上映時間2時間10分に対し、2時間50分(予想)となった「新しい映画」である。現時点では試写会やイベント用の先行公開バージョン(2時間40分)しか完成していない。試写の前説では「公開時には3シークエンス7分とクラウドファンディング参加者一覧3分を追加」と言われていて、公開が楽しみである。
3時間近くは生理現象が気になる尺なのだが、2時間40分は驚くほど長さが気にならない仕上がりとなっていた。方法論としては当然「新作カット」を組み込んでいる。通常そういう処置をすると、前後で生じる落差が気になったりする。ところが、それがまったく気にならない。もともとコンテ段階で用意されたエピソードを組み込んでいるためでもあるが、「新しいカットが組み込まれることで、前からあったショットが新しい意味性を帯びる」点に、何より深い感銘があった。
すでに広く知られているように、主人公すずが遊郭に迷い込んだ体験を中心とする「心の機微」が加わり、「夫婦になること」「居場所を見つけること」といったストーリーの軸が、まったく違って見えてくる。まさに「別の映画の誕生」である。だからありがちな「ディレクターズカット」「完全版」といった趣向とは違う(それらが初公開版より見劣りする場合が多いのは、よく知られている)。
当初は「長尺版」と呼ばれていたが、それも今となっては何かが違う。もちろん監督も公式サイトも「別の題名をつけた“もう一本の映画”」を強調しているし、理屈では分かっていたのだが。「映画体験」の点でまた次元が違っていた。本タイトルは何度となく現実世界に「奇跡」を起こしてきた。それがまたひとつ増えた感覚である。
これは自分の長年の探求にも深く関わっている。それは「なぜ日本の商業アニメーションは(テレビ作品でも)“映画にしたい願望”があるのか」「そもそも”映画にする”とは何か」の探求である。「劇場でかかるから映画」や「2時間前後の長尺だから映画」「序破急、3幕でクライマックスがあるから映画」など定型の問題ではなく、本質が知りたい。東京国際映画祭の仕事を通じ、暫定的でも分かっていることをまとめる時期と思っていたところに、最適かつ得がたいサンプルが誕生したとも思った。
今回の場合、「前の映画を否定するものではない」点が大きなポイントだ。“映画にする行為”は、ショット(撮られた素片)とショットを組み合わせ、カット(切断編集)する方法論により、「一本の時空間に編み上げること」を意味する。「切ることで映画にする」と言われるほどで、「空間をカメラのフレームで切る」、「時間にハサミを入れて切る」、つまり「時空間を切りとって再定義する作業」が「映画にすること」なのである。
「何を当たり前のことを」と思われるかもしれないが、これを深く考えたかどうかで、明らかに「映画としての仕上がり」は変わってくる。「娯楽性のあるイベントを羅列した遊園地のアトラクションに類するもの」か「動かしがたい現実に対して切り結び、異議申し立てをしつつも、何か新しい認識や知見に至るもの」か、そうした差違が発生する。
その差違の有無は、「映画を見終えた後に、自分の生きるべき時間と空間が違って見えてくる効能」として顕現する。これは高次の「生命をふきこむアニメーション」に該当する。「アニメーション映画」は「作画レベルの生命」を地味に積みかさねて、この「高次の生命感覚」を獲得できるメディアではないか……。それが、20年近くこの問題を考え続けてきた自分なりの到達点だ。片渕須直監督の「この世界の片隅に」関連の発言にも、同じような意識が散見される。
結局は「映画それ自体がひとつの人格のように“カメラはこれを切りとってきた”ないし“情報の取捨選択でこれを伝えたい”と観客に対峙し、新しい価値観を示せるか」が問題になる。強調しておきたいのは「監督の人格」ではなく「映画の人格」である。監督は、あくまでもその人格を宿すための技術的方法論レベルのディレクションに徹し、黒子としての客観性をもって時空間を編み上げたほうが「映画人格の強度」が上がるはずだ。そうやって完成した「時空間」こそが「映画内世界」の正体なのである……。
などと、今回2通りに編み上げられた「2本の映画」を通じ、いろんな観点の思考が次々にわいてくる。その点で、得心のいく事例に感慨深く思った。まだもう一度、公開時に「驚きの発見」が予定されているわけだから、その点も楽しみに思っている。
なぜ「感慨深い」のか。それは、こうした自分の20年近い考察の契機のひとつが、他ならぬ片渕須直監督の映画デビュー作「アリーテ姫」(01)にあるからだ。今回の新作公開に合わせて「KAWADEムック 片渕須直」(河出書房新社)が発刊される()。編集部からは参加オファーがあったが、先述の事情でご辞退しつつ、代案としてまさにこの原点にあたる「アリーテ姫」のときの取材原稿と論評の再録が実現した(論評はSF的に「アリーテ姫」を読み解いた点で片渕監督からの希望だったと聞く)。
そのインタビュー原稿はキネマ旬報掲載分ではなく、自分の個人誌「ロトさんの本Vol.7」用に、ほぼノーカットとして加筆、監督チェックも受けていた。ゲラを確認すると、監督のブレのなさに改めて感嘆するとともに、「なぜ次回作が平安時代なのか」のヒントも発見できた。何だか今回の「さらにいくつもの」に響き合うような点でも、感慨は深い。
そしてアニメスタイル編集長・小黒祐一郎氏のお誘いで「この世界の片隅に」の企画書用の、片渕須直監督の特質を書いた紹介原稿も関係者のご厚意で再録される運びとなった。2011年の夏、まさに東日本大震災の直後に書いた文章である。「なぜこの映画が必要とされるのか」の観点で、自分なりの「願い」をこめた。1000日をはるかに超える上映期間、予想よりもはるかに多くの観客に感銘をあたえ続け、現実世界に響きあって「何か重要なものごとを変え続けていく(この先もずっと)」なる「現実の奇跡」をもたらした、この映画プロジェクト。その「願いの連鎖」に加われた点が、今はもっとも感慨深いのである。

氷川竜介の「アニメに歴史あり」
[筆者紹介]
氷川 竜介(ヒカワ リュウスケ) 1958年生まれ。アニメ・特撮研究家。アニメ専門月刊誌創刊前年にデビューして41年。東京工業大学を卒業後、電機系メーカーで通信装置のエンジニアを経て文筆専業に。メディア芸術祭、毎日映画コンクールなどのアニメーション部門で審査委員を歴任。
作品情報

-
広島県呉に嫁いだすずは、夫・周作とその家族に囲まれて、新たな生活を始める。昭和19(1944)年、日本が戦争のただ中にあった頃だ。戦況が悪化し、生活は困難を極めるが、すずは工夫を重ね日々の暮らし...
-
![この世界の(さらにいくつもの)片隅に (特装限定版) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41Ox7PsbaxL._SL160_.jpg)
この世界の(さらにいくつもの)片隅に (特装限定版) [Blu-ray]
¥10,780 ¥8,632

-
![この世界の(さらにいくつもの)片隅に [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/415HF6dPgsL._SL160_.jpg)
この世界の(さらにいくつもの)片隅に [Blu-ray]
¥5,280 ¥4,228

-
![この世界の(さらにいくつもの)片隅に [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41xjukUup7L._SL160_.jpg)
この世界の(さらにいくつもの)片隅に [DVD]
¥4,180 ¥3,418

-

「この世界の片隅に」さらにいくつものサウンドトラック
¥3,190 ¥2,566

特集コラム・注目情報
関連記事
イベント情報・チケット情報
- 2024年8月3日(土)
- 2023年10月28日(土)
- 2023年8月5日(土)
- 2023年3月18日(土)
- 2022年8月6日(土)