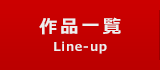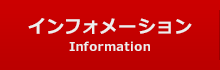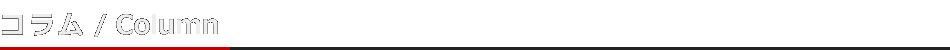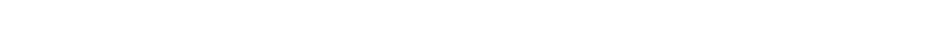「あまねく人がいる」生きた都市の感覚
 ところが庵野秀明は、その「記号化」による思いこみの逆をいき、自分が日常で思い入れをして観察しているディテールにこだわり、「これを見よ!」と提示する。そんな「逆の発想」も作家性のうちだ。
ところが庵野秀明は、その「記号化」による思いこみの逆をいき、自分が日常で思い入れをして観察しているディテールにこだわり、「これを見よ!」と提示する。そんな「逆の発想」も作家性のうちだ。
人間の鼻の穴でさえオミットされてしまうアニメ世界の記号化。都市の場合、水彩画の背景を中心に描かれている。ところがなぜか『エヴァ』の電柱は主線(アウトライン)のあるセル描きの「キャラクター」として配置されている。よく見てみると「高圧線鉄塔」や「信号機」など「電柱の仲間」もセル描きになっているではないか。
こうした処理をされると、人間の頭脳は「ふだん目がスルーしているノイズが前景化している!」と驚く。そしてあたえられた情報から「意味」や「ルール」を読み解こうと積極性を発動し、それが画面内への没入感の触媒となる。元来「眼」とは生存本能に基づき、その種の変化をつかみ、適応のための手がかりを得るために発達したものなのだから、当然だ。「電柱がキャラ?」と考えを深めると、「なるほど、確かにこれも生きている」という次の手がかりもつかめる。電柱には電信柱と電力柱の二種があるが、それは都市の「神経」と「動脈」を走らせるパイプライン、生命線が本質なのだから。
さらに「電柱がそこにある」という実存は、「設計した人がいた」という過去への想像力を喚起させる。建立した作業員もいた。どんな電柱も垂直に立ってはいないならば、傾きの許容マージンを判断した人もいた。家々まで配線を敷設工事した人がいた。動作確認した人がいた。この「あまねく人がいるがゆえに、都市は崩壊せずに支えられているのだ」という感覚は、エヴァシリーズのみならず庵野作品に通底している。そんな時間と空間の連なりから「ドラマ」を感じる人もいるだろう。
庵野秀明監督は、おそらく少年時代からそうした時空間の想像力と、科学技術への憧憬混じりの「眼」で都市のディテールを見て「原風景」を構築してきた人のはずだ。エンジニア経験がある筆者はそこに共感を覚えるし、科学技術の産物である「映画」に興味関心のある方なら、間接的にでもこの感覚は伝わっていると思う。
一方で、こう言葉にしてしまえばメッセージとして「それだけのもの」に堕落しかねない。抽象度の高い「画」に置き換えて示されているがゆえに、意図は表層化されず的確なバランスの触媒となって脳内の奥に染みわたり、観客の心の奥底にあったものを解き放つ。 これが映像の妙味なのだ。『エヴァンゲリオンシリーズ』を見た後に街中を歩いてみれば、ふとした瞬間に電柱のディテールが目に飛びこんでくるようになって、驚くかもしれない。それは「つまらないと思いこんでいた日常世界が異世界に変わった」ということなのだ。ということはエヴァ鑑賞によって、そんな魔法がかけられたということだ。
この種の「異化効果」は、デジタル手持ちカメラを駆使して「都市と女子高生の日常」に新たな視点を持ちこんだ映画『ラブ&ポップ』(98)や、故郷・山口県宇部市をシネマスコープの横長な画角で切り取り、見つめなおした映画『式日 SHIKI-JITSU』(00)など、20世紀末の『新世紀エヴァンゲリオン』終了直後に撮った実写に、ひときわ顕著である。
カメラポジション、移動感、編集を加えることで、見知った風景でも、まったく異なった様相を見せ始める。鮮やかな「切り口」によって、正体や実像を現す日常。庵野秀明作品を楽しむには、まずこうした発想と視点そのものが「作家性」であるという前提に立ってみるのが良いのではないか。
今回はそんな庵野ビジョンをまとめて体感できる、またとない好機である。