![]() 2019年1月2日(水)19:00
2019年1月2日(水)19:00
押井守監督の“企画”論 縦割り構造が崩れた映像業界で、日本の映画はどう勝負すべきか

イメージを拡大
「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」「機動警察パトレイバー2 the Movie」などエポックとなる作品を手がけ、アニメーションや映画に関する著書も多い押井守監督。自他ともに認める映像マニアであり、常に自覚的に映像をつくり続けてきた押井監督にとって、最近の映像業界はどのように映っているのだろうか。「監督にとって2018年はどんな1年でしたか」と聞くと、押井監督は淡々とした口調で語りだした。(取材・構成:五所光太郎/アニメハック編集部)
2018年の前半は仕事でかなり忙しかったんですよ。これから世にでる作品で、まだタイトルは言えませんが、ある実写作品の作業をずっとやっていて、2月ぐらいまでは脚本をバタバタと書きまくっていました。3月から本格的に撮影の準備をはじめて、4月末から5月にかけて撮影。それからいろいろと後始末もして、今年の前半はけっこう活躍したと思います。今年の後半はその逆で、まるっきりの空白状態。それゆえにいろいろ考えることはできたし、たくさん動画も見ることができた。その辺りも含めて面白い1年だったという感じですかね。
しかも今年の夏はあまりに暑かったから、6月以降は完全に記憶がとんでいるんですよ。ただ生きているだけでいっぱいいっぱいだったというか、何を読んで何を見たのかあまり覚えていない。覚えていることといえば、あまりに暑くて僕としては珍しく映画館に何度か足を運んだぐらいです。どうしても見たい映画が何本かあって、もちろん「ブレードランナー2049」(17)が本命だったんですけれど。「ブレードランナー2049」は、とにかくよかったですね。言いたいところはいろいろあったけれど、私(わたし)的には久しぶりに映画館で見るべき絵と音響の映画だと思った。10年に1本の映画と言うに相応しいできで、「メッセージ」に続いて、さすがにドゥニ・ビルヌーブ監督はすごいなと。
2018年の前半に実写映画を久しぶりに1本撮った経験と、その後半にさまざまな映像を見まくって考えたことで分かったのは、映画の仕事の中身が随分と変わってきたなということです。それも、ここ数年のあいだでドラスティックに変わったといっていい。映画に関わる人間は例外なくその大きな変化の渦中にいるわけだけど――。
その変化は何かというと、これまであった映画の縦割り構造が完全にくずれて、横割りになったということ。言い方を変えると、映画が必ずしも映像の仕事の一等賞とは言えなくなった。これまではある種のヒエラルキーとして、アニメでも実写でも劇場用の長編映画をつくるのがいちばん偉いんだという意識が、僕もふくめてどこかにあったと思うんですよ。それに続いてテレビやビデオの仕事があるっていうね。それが最近はネット配信というものが加わってきて、実は一昨年ぐらいから僕のところにくる話って、ほぼ配信がらみなんです。100パーセントといってもいい。僕がその方面に向いている監督なのかはおいておくとしても、明らかに映像の発注元が変わってきた。
映画をつくっている側からすると、「何をつくったら当たるか」がいちばん気になると思うんですよ。製作会社、プロデューサー、監督、それに関わる人たち……映画.comさんのようなメディアの人たちもそうだと思うんだけどさ。それが今は誰も予想がつかないわけだよね。これは、この間の「カメ止め(カメラを止めるな!)」のヒットとも関連する話なんだけど、何が当たって何が観客に求められているのか誰にも分からない。なぜそういうふうになってきたのかを、ずっと考えてきたんだよね。というのも、僕はまだまだ映画監督をやめる気はまったくないので、これからどうやって映画をつくっていこうかというとき、そうしたことを考えざるをえないと思ったわけ。「将軍は前の戦争で次の戦争を戦う」という有名な言葉があるとおり、どんな人間も必ず自分の成功体験に引きずられて、自分のやり方をなかなか変えられないものだからね。
「THE NEXT GENERATION パトレイバー」を一緒にやった、僕のちょい下にあたる辻本(貴則)、湯浅(弘章)、田口(清隆)も、今はけっこう忙しくしていて、20年近くたって、ようやく映画監督として食えるようになってきた。といっても、辻本は「バイオハザード:ヴェンデッタ」(17)をやったあとに「ウルトラマンR/B」(18)を撮ったり、湯浅は深夜ドラマの「ワカコ酒」(15~17。19年にSeason4放送)を撮っていたりする。映画監督の仕事も昔ほどシンプルではなくなって、何をやるか分からない部分があるんだよね。デビュー作で評価されても、すぐに次の映画が決まることが少なくなってきた。
三池(崇史)さんは、映画の仕事が持続する日本でも珍しい監督になったけど、彼みたいに次から次へと映画を撮れる監督はまずいませんからね。本広(克行)君なんかも、最近は舞台やビデオ、ネットムービーや深夜ドラマなどをやりながら、映画館でかかる映画もつくっていて、いろいろなオーダーに応えている。それぐらい今の映画監督は何をやるか分からないわけです。
僕らの仕事というのは、世の中の都合にあわせてやるしかなくて、発注がきてはじめて成立する。でも今は、発注する側も実は何をどうしたらいいか、よく分からなくなってきている。それは企画の中身だけじゃなくて、これは配信でやるべき企画なのか、映画館にかける映画としてつくるべきなのか、テレビドラマなのかオリジナルビデオなのか……その根拠みたいなものがよく分からなくなってきていると思うんだよね。

2018年に上梓した著書「シネマの神は細部に宿る」(東京ニュース通信社刊)。
イメージを拡大
映像をつくる側としては、最終的にやることは一緒なんだけれど、何を目指してつくるべきなのかが違っていないといけない。つまり、お客さんの側から見ると、映像の出口によって求めるものが変わるんだよね。映画館で見たい映画、配信で見たい映画、レンタルビデオで見たい映画、ネットやYouTubeで見たい映画……。そういう意味で映画の縦割り構造は崩れて、横割りの構造になったんだと思う。
かつて映画が縦割りだった頃は、洋画や邦画、実写やアニメというふうに分かれていても、基本的に映画は小屋(映画館)で見るものであって、それより値段的にも中身的にも下がるものとしてテレビドラマやテレビアニメというものがあった。で、第3の選択肢としてオリジナルビデオがあるという今から思えばシンプルな構造だったと思う。映像の中身も求めるものによって変わるから、例えばオリジナルビデオだったら、何回も見ることが前提になっているつくりだから買ってもらえるわけでさ。あるいは、もう見るか見ないか分からないけど、その作品が好きだから買うっていうね。ブルーレイボックスを買っても、ちゃんと全部を見ている人はほとんどいないと思うわけ。ただ、隣に並べておきたいというか、自分の好きなものを側においておきたいのは人情だし、一種の所有欲を満たすという。そんなふうに、これまでは一定の根拠をもっていたと思うんだけど、今はそれがよく分からなくなってきていると思うんだよね。
重ねて言うと、映画が映像の仕事の一等賞とは言えなくなった。日本で豪華につくるといっても、海外の映画には勝てないでしょう。最初から製作費の桁が違うから、普段見られないような豪華なものや、すごいアクションが見たかったら、マーベルやDCあたりのハリウッド映画を見たほうが絶対にいい。映画1本見るのは、同じお金ですから。では、日本でつくられる映画には何を求めるかといったら、映画館でしか体験できないものって、僕はいくつかしかないと思う。そのひとつが、「みんなで一緒に見る」ということで、みんなで同じノリになれるっていうさ。その典型が「カメ止め」だと思う。
フォトギャラリー
フォトギャラリーへ
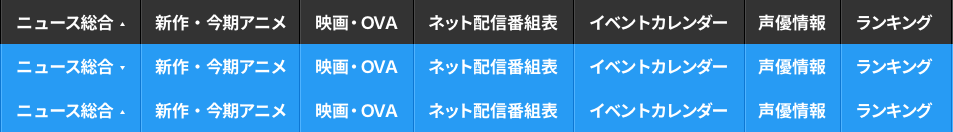

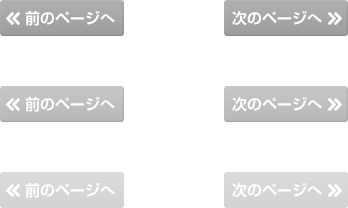






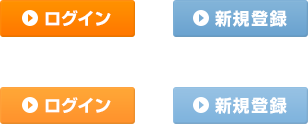







関連するイベント情報・チケット情報はありません。