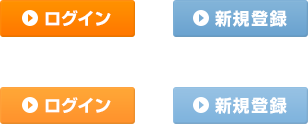![]() 2023年6月8日(木)19:00
2023年6月8日(木)19:00
プロデューサーの仕事は“考える”こと 川瀬浩平が独立した理由 (2)
――お話しづらい部分かもしれませんが、具体的にどう頑張られたのでしょう。
川瀬:「シャナ」の原作が進んでいないとき、あまりアニメに間があいてしまうとお客さんの興味がうすれてしまうからとビデオシリーズをやったんです。いやらしい話ですけどビデオの単価はテレビアニメよりも高くて、もちろん制作費も高くなりますが、テレビアニメの何話収録いくらに比べると、ビデオは1話しか入っていませんから、そのぶん利益率は高くなります。
「シャナ」のビデオシリーズは皆さんに買っていただけたおかげでそれなりの数字もついたので、それを出資者の皆さんにみせて人気が続いていますとしめすことができたんです。もちろんシリーズ全体を見ると、ちょっとずつ下がってきていますが、次はファイナルまでやりますので最後までやるんだったら見てみようというファンもでてくるはずです。しっかり宣伝もしますので、そうしたら休眠ユーザーもふくめて、さらに人気があがってくると思うんです――みたいなことを、自分の会社の偉い人をふくめ出資者の皆さんにプレゼンしてお金を集めて、意地でも最後までやるっていう。「食戟のソーマ」なんかもそうで、途中から土肥プロデューサーに代わってもらいましたけど原作の最後までやることができました。あと、最初は中山プロデューサーがやっていたOVAの「ストライク・ザ・ブラッド」も――。
――「ストライク・ザ・ブラッド」は驚異的に続いていましたよね。
川瀬:驚異的でした。
――劇場上映ものなどをのぞく、昔の意味でのOVAがなくなりつつある今、テレビシリーズのあとOVAシリーズが第5期まで続いていたのは作り手とファンのあいだでとてもよい循環がおきていたんだろうなと思っていました。
川瀬:本当にファンの方に支えられ続けたって感じですね。作品自体もとても愛されていましたし、とくに姫柊雪菜というキャラクターをみんなが好きになってくれて。とにかくパッケージの数字が下がらなくて、下がらない以上やめる理由はないっていう状態でした。
――購入して楽しむOVAは、基本無料のテレビアニメとは違ったファンのモチベーションと製作のハードルがあると思います。それを超え続けてきたのはすごいと思います。
川瀬:たしかにOVAには作品を好きになってもらい、それ自体がいいのかどうかは議論がわかれるところですが、自分たちが買い支えないといけないと思っていただかないといけないというハードルがあります。それぐらいに思ってもらえる作品になったのは、キャスト・制作陣はもちろん、先代の中山プロデューサーらが作品に愛情を注ぎこんだ結果だと思います。
僕は途中から中山さんの代わりに入ることになって、ここまできたんだから完結までやりたいと思って続けてきたのですが、ふと気がついたら原作がなかなか終わらないから、原作者の三雲(岳斗)さんにあとどのくらいで終わるか聞いたら、「いや、アニメが終わらないから原作も終われなくて」と言われて、僕らのせいだったのかってうれしかったですね(笑)。三雲さんからは、一応ひと段落つきそうなのがここですと教えてもらい、僕らもそこまで頑張りますとお話しし、ファンの方が買い支え続けてくださったおかげでゴールまでたどりつくことができました。さすがにここで数字は言えませんが、同業の方にセルとレンタルの数字を話すと「今の令和に!?」とビックリされます。しかも、その数字がまったく落ちずに昨年7月の最終巻まで続きましたから、本当にすごい作品だなと思います。
■「負けないバクチ」をするために
――「プロデューサーの仕事は考えること」に関連して、作品を企画するときのことを聞かせてください。企画書にはプロデューサーが何を考えているのかが書かれていなければいけなくて、川瀬さんがつくる場合はもちろん、他の人がつくったものを見るときもそうした部分に注目されるのかなと思いました。
川瀬:きれいに製本された見栄えのいい企画書を見ることが最近多いんですけど、そういう企画書にかぎって中身がなかったりすることもあるんですよね。「で、結局、何がやりたいの?」って。若い人から企画書を見てくださいと言われて目を通させてもらうと同じようなことを思うことが多くて、原作ファンだけをターゲットにせず、どこのお客さんをターゲットして作品をどう大きくしたいのかが見えないですよと言うと、「あっ」って言われちゃうこともあって。
さっき、「この原作が大好きですから!」では駄目だという話をしたとおり、僕らの仕事はそこを考える仕事ですから、厳しい言い方になりますがそういう企画書をだしても「ああ、この作品大好きなんですね」で終わってしまいます。
――個人的には、本当に自分が好きだという熱量でつくられたものも良いなと感じて、そういう作品は見ていて好感がもてることも多いです。それがビジネス的に成功するかどうかは分かりませんが。
川瀬:発端は好きで全然いいと思うんですよ。ナチュラルボーンでそれができる人でいうと、元同僚で今はグッドスマイルフィルムの小倉(充俊)さんなんかは、そういうタイプのプロデューサーだと思います。自分の好きとお客さんの嗜好が一緒なはずという自覚があって、その熱量で現場にもアタッチできるので、現場も一緒に熱くなれる。そういう空気感をつくれるプロデューサーさんという印象をもっています。そこまでできる人はいいんですけど、普通はなかなか上手くいかないので、好きだけでなくちゃんと考えたほうがいいとは思っています。小倉さんも好きだけでなく、いろいろ考えられているはずですからね。
もちろん熱意は大事です。ただ熱意だけで突っ走ってすかされたり、悪いときは騙されたりっていうぐらいだったら、熱をもったうえできちんと考えて企画にアプローチする方が、より確実にお客さんが喜ぶものがつくれる気がします。あくまで喜ぶお客さんの代表として自分たちがいる。ビジネスプロデューサーの立ち位置ってそこだよっていうことですよね。一方、制作のプロデューサーは、監督やスタッフたちと一緒に、クライアントからきた企画をクライアントサイドに納得してもらいつつ彼らのやりたいフィルムとしてかたちにするのに注力するというフィルムに特化した役割や考え方になります。
僕が発注する場合、最終的にビジネスに特化する考え方になりますから、そこから逆算して「こういうフィルムをつくってもらえませんか」となる。それを現場がフィルムにするときの落としどころは制作のプロデューサーと考えなければいけなくて、例えばJ.C.STAFFの松倉さんとはそういうことが上手くできていたのかなと思います。
――なるほど。ビジネス面を川瀬さんがしっかりかためて、そのオーダーをうけて実際につくるための方針は松倉さんと2人で相談すると。
川瀬:お客さんにこんなふうに喜んでもらいたいから、僕はこういうことを言っているんですと話して、松倉さんはそれをちゃんと理解したうえで現場にわかる言葉で落としてくれる。反対に、現場からこういうものをつくりたいから、ここはこうしたいというようなことは、松倉さん経由で僕のほうで承る。それが原作ものの場合は、僕から原作サイドの方々に、「この部分は原作の意図はわかりますが、そのまま映像にするとそぐわないから別のアプローチをすることは可能でしょうか。できればそうさせてください」と話す。原作サイドもクリエイターですから、そこで別のプランがでてくることもあって、そのときは松倉さん経由で現場とすりあわせながらどこを落としどころにするのかを探る――そういうことを常にやりながらハブとなることで、最終的にお客さんの喜ぶ映像を届けるというのがビジネスプロデューサーなのかなと思っています。クリエイターにも原作サイドにも、そしてお客さんにもがっつりいかないけれど、それぞれの意見をどのようなバランスでやればいちばんハッピーになれるかを探すというフラットな立ち位置です。
――ビジネスプロデューサーとしては、「シャナ」の話のときにもあったように製作委員会の人たちに納得してもらい、最大限リクープするように考えることも大事になりますよね。
川瀬:「フィルムビジネスって結局バクチだな」と思いながらも、「負けないバクチをしなければいけないな」と常に思いながらこれまでやっていました。大穴狙いで「大バクチじゃー」みたいなことをやって人のお金を運用するっていうのは、僕は性格的に向いてないと思っています。
僕の場合、出資者の方にたいしては企画についてある程度納得してもらいながら、「こういうフィルムになりますから、これぐらいの数字が(強調して)予想できます。そのための努力をします」となるたけ誠実に説明するようにします。ま、結果は結果なんで、ふたを開けたらごめんなさいはあるかもしれませんが、それでも最大限“負けない試合”をするために頑張る。その結果、大儲けはできませんでしたが、とりあえず出資者にほぼほぼ全額が返ってくることになりました。ちょっと足りていませんが、フィルムという資産が残っていますから、これを何年か運用することで黒字化はみこめるでしょう。ということはタネ銭は残りましたよね。じゃあ、次の作品にも出資しませんかってことが言えるっていう。それが僕にとっての“負けないバクチ”で、そのために最低限“負けない試合”をする。これが、さっきお話した「シャナ」のようにシリーズが続く要因でもあって、大負けはしないので次にもう一回できることが多かった記憶があります。要は、継続シリーズをつくることで前のカタログ(※過去作品)も盛り上がり、プロジェクト総体としても数字があがってくる。だから、続きをやりませんかという提案ができる謎の錬金術をやってきたのかなと(笑)。事前にいただいた質問状をもとにいろいろ考えると、自分の仕事はそういうことだったのかなと思いました。
――ありがとうございます。大きいのは作品が残っていくということなんですね。お金を生み出してくれる作品が残ると。
川瀬:イチかバチかで1クールやりました、駄目でした、ああ駄目だったねえ、だけだと困りますからね。駄目だった場合でもフィルムは残っているからマネタイズはできるかもしれませんが、数字が大きく負けてしまった作品が今後どれだけ回収できるかは分かりませんし、会社によってはこんなにマイナスになると次はできないと上から言われたみたいなこともありえます。僕自身も「あいつに張ったら負けた」「あいつにお金を出すのは怖い」と思われたくないですし。そのためにも最大限“負けないバクチ”をして、「川瀬さんに張っておけば、少なくとも大負けはしないかな」みたいな感じに思ってもらえればっていうところはありましたね……これまでやってきた営業的なことを全部しゃべっちゃいましたけど(笑)。フリーになった今だから言える話も多いですが、思い返すとそういう思考で仕事をしてたような気がしました。
――企画書には、今言われたようなプランも盛り込まれていてほしいというわけですね。そのうえで、作品内容に見合った制作費などを確保するという。
川瀬:もちろんコストバランスもですね。制作会社さんの選択もそうですし、今回はこういう作品だから監督や脚本は誰にお願いしましょうかみたいなスタッフィングの話も当然制作会社さんと相談します。
さっき僕は自分の立ち位置を「クリエイターにも原作サイドにも、そしてお客さんにもがっつりいかない」と言いましたが、そこに出資者も加えて、みんなとりあえず作品にかかわった人間が8掛けぐらいで満足したねっていうプロジェクトが良いプロジェクトだと思っているんですよ。あくまで「僕は」ですけれど。
――どういうことでしょう。
川瀬:100パーセントは満足できなかったけれど、みんなおおむね満足しましたっていうのが良いプロジェクトなんじゃないかと、僕自身はまずはそれを目ざしてやっているところがあります。皆さんに8掛けで満足してもらうのは大変なことなので、そのためにものすごく頑張るわけですけどね。
例えば、宮崎駿監督や庵野秀明監督のように強烈な個性のあるクリエイターがいて、その人の100パーセントを目ざしたほうがみんなが幸せになるかもしれないのだったら、たぶん僕はそうすると思いますが、そういう方々はなかなかいらっしゃいませんよね。であれば、作品に関わる人たちがまんべんなくそれぞれの仕事に満足できるプロジェクトにするのがいいんじゃないかと思うんです。作品がそこそこヒットすれば、原作の後押しになって数字もついてきますし、クリエイターは作品が名刺代わりになります。製作委員会も大勝ちできれば万々歳ですが、少なくとも負けなければ次の作品に出資ができる。お客さんにも、あのシーンとあのシーンはちょっと気に食わなかったけれど、この原作をアニメにしてくれてありがとうと思ってもらえれば、僕の眺望としてはいい仕事をしたかなと思えるんです。
――それぞれの8割の満足を目指すって、すごく納得できますし良いですね。例えば、原作や出資側の意向だけをききすぎてクリエイターがフラストレーションを溜めるのもよくないし、逆にクリエイターが原作やお客さんのことを無視して自分のやりたいようにつくりすぎるのもよくないと。
川瀬:8掛けの満足だと関係者に次もやりたいと思ってもらいやすくて、シリーズを続ける理由になることも多いんですよ。みんなこれだけ満足しているんだから、もっと続けてより満足したいと思ってもらえるのが、それぐらいの塩梅なのかなと勝手に思っています。もしかしたら、そう思っていない人もいるかもしれませんが(笑)
――みんなが8割満足するバランスを目ざして最適化するために動くのが、ビジネスプロデューサーとしての川瀬さんのお仕事のひとつになるわけですね。
川瀬:25年やってきて、ビジネスサイドの仕事ってそういうことかなと僕は思っています。冒頭にお話した独立した理由のひとつである「お客さんをより楽しませたい」というのは僕が仕事をするうえでの根っこの部分なのですが、それを拡大解釈すると、携わってくれた人みんなが満足して、「川瀬と仕事をしてよかったな」と思ってもらえるために自分がどれだけ汗をかけるかっていうことが、僕の仕事のモチベーションでもあるのかなという気はしますね。……好き勝手言いながら、最後にええかっこしいなこと言ってますけれど(笑)
■「プロデュース」とクレジットする意味
――事前の質問状にも書かせてもらった、川瀬さんが携わっている作品にクレジットされているプロデューサーとプロデュースの違いについて聞かせてください。すでに答えはでている気がしますが、ここまでうかがってきたことをしている責任として「プロデュース」としているのかなと思いました。
「企画」は出資している会社の偉い方、プロデューサーは製作委員会に参加している方々の名前がクレジットされていて、プロデューサーがたくさんクレジットされている作品だと、企画発案者として責任をもって作品を大きく担っているプロデューサーは誰なんだろうと思うときがあるのですが、川瀬さんが携わっている作品には「プロデュース」というクレジットがあって、ひとつの意思表示としてつけられていたのかなと思っていました。
川瀬:深く考えてくださっていますが、僕の答えはけっこうシンプルなんですよ。まさにその通りでもあるんですけどね。その前にまず前提をいうと、僕自身は、会社員であるプロデューサーは名前をださなくてもいいんじゃないかと思っているんですよ。
作品のクレジットは、フィルムが名刺代わりになるクリエイターのためのものであって、極論を言っちゃうとクリエイター以外は別に載せなくてもいいんじゃないかと思っています。クレジットがあることでクリエイターは「あの作品をやりました」と言えますし、その映像を見て「この人と仕事をしてみたい」と思う人の手がかかりにもなりますから、クリエイターは絶対クレジットに入れるべきだと考えています。そんなことを言っておいて、今は僕も独立しましたからクレジットに入っていて良かったって思うんですけどね(笑)
――(笑)
川瀬:でもまあ、当時は会社員ですから、会社に守られている人が、いちいち名前をいれなくてもいいんじゃないかなと思っていた、というのが基本的な僕の考え方なんです。ただ、お金をだす「企画」の人は別ですよ。その人たちは、会社にたいして(お金をだす承認の)ハンコを押すという大きな責任を担っているわけですから。
なのにお前はなぜこれまで名前をいれてきたのかっていうと、要は責任ですよね。「はい、この人責任者です」「フィルムに不満があったら文句はこちらに」ぐらいの感じでした。作品がこけようが何しようが首になるわけでもない、リスクを背負っていない人間ではありますが、一応フィルムに携わった責任者として名前をいれろっていうことかなととらえて、これまで名前をいれさせてもらってきました。
前提が長くなりましたが、プロデュースと入れるようになったきっかけは単純で、「灼眼のシャナ」のとき、前述の中山さんと僕がクレジットされると同じ会社から2人もプロデューサーとして並ぶことになって、個人的にそれは避けたいなと感じたんです。カッコ悪いし出たがりかよって(笑)。ただその当時、中山さんにはプロデューサーとしてオープニングにクレジットされることで、作品をプロデュースすることに対して責任を持ってもらいたいとも思ったんです。で、2人連名はダサいし僕はどうしようとなったとき、プロジェクトの責任者として「プロデュース」というクレジットはありかなと思い、僕だけだと偉そうだと思ったので、製作委員会の幹事のプロデューサーである川瀬、制作チームのトップであるJ.C.STAFFの松倉さんの2人を「プロデュース」としてクレジットし、第2期からは原作サイドのトップとして当時「電撃文庫」の副編集長だった小山(直子)さんを入れた3人になりました。各セクションの頭(かしら)がプロジェクトプロデュースとして動いて、各セクションの責任は中山さん、三木(一馬)さんらプロデューサー陣が担う。それとは別にスタジオの制作プロデューサー、出資会社の方たちは別途クレジットするってかたちが個人的にけっこうしっくりきたので、以降そうしていたということだったんです。
――なるほど。もともとは中山プロデューサーをオープニングにクレジットさせたいというところからはじまったわけですね。
川瀬:若い人を引っ張り上げるじゃないですが、そういう立場に身をおいてもらうことでより責任感をもって作品に携わってほしかったんですよね。プロデュースという名称については、その前にやった「スターシップ・オペレーターズ」では局の要望でゼネラルプロデューサーという肩書きにしたこともあって、総合プロデュースとかも分かりやすいかとか考えたんですけど、結局プロデュースぐらいがさらっとして良いんじゃないかと(笑)
――オープニングの最後のほうにプロデュースとあると、この方々が作品の責任者なんだなと見ていて良く分かります。
川瀬:まあ、外からも見えやすいですよね。繰り返しになりますが、どうせクレジットを載せるのならば責任の所在がはっきりするかたちのほうがいいやと思ってやった感じで、あまり難しくは考えていなかったんですけどね。
■アニメ業界、四半世紀の変化
――ここまでで十二分にお話をうかがえていますが、もう少しだけお話をうかがわせてください。25年アニメのお仕事をされてきて、アニメにまつわる状況の変化についてどう感じてらっしゃいますか。
川瀬:大きく変わりましたよね。僕は1997年頃からこの仕事をしていますが、制作システムがフィルムからデジタルに変わったのはまず大きかったなと思います。97年に最初に仕事をした「神秘の世界エルハザード」という作品はフィルムでしたが、制作の方がクレジットの名前が間違えていたからまたフィルムを焼き直さなければいけないなんて言っていたのを覚えています。そのすぐあとぐらいからデジタル化が進んでいって、完全に移行したのは2003、4年ぐらいだったかなと思います。
当時のOVAって、完パケをつくったらそのフィルムをもって全国で試写会をやって予約をとることをしていたんですよ。でも、それでは効率が悪かったので、テレビで試写会をやろうというビジネスに変わっていったんです。それが今の製作委員会方式の深夜テレビの源流になりますかね。
デジタル化が本格的になるちょっと前の2000年前後に、ビジネス的にはDVD特需がありました。それまではLD(レーザーディスク)だったのが、DVDという新しいメディアがでてきたことによって、レコードメーカーが潤う時期があって、そこで入ったお金を新作のアニメにつぎ込んで、またビデオを買ってもらうというビジネスが成り立つようになったんです。
――なるほど。
川瀬:DVD特需で盛り上がっている流れとは別に、97年からはじまったアニメ「ポケットモンスター」が2000年前ぐらいから海外でもりあがって、それまでも「ドラゴンボール」や「セーラームーン」は海外で人気がありましたが、海外で日本のアニメが更に注目されるようになり、今でこそ収入の大半を占めるようになった海外からの収益が少しあるみたいな状況になり、「アニメ・エキスポ(AX)」などの海外イベントが徐々にもりあがっていったのもその頃だったと思います。まあ、海外でのアニメバブルはそのあといったん終わったりもしたんですけれど。
その後、2008年ぐらいにメディアがDVDからブルーレイに切り替わりましたが、DVDのときのように全体のパイは増えず、むしろマニアックになりすぎてしまって、ソフトを買うのが好事家のものになっていったように感じています。
そして、2014、5年ぐらいから映像ビジネスで配信の存在感が増してきました。日本の住環境で映像ソフトをコレクションするのが大変なこともあって、配信という作品をクラウドで引っ張ってこられる時代になると、みんなDVDやブルーレイを買わなくなっていきました。ただ、配信ビジネスの方々はカタログ(※新旧ふくめた作品ラインナップ)がないとやっていけないので、そうしたアプローチが増えてきました。と同時に海外方面では中国からの需要が爆発的に増えて、映像ソフトの売り上げが下がってきたのと入れ替わるように海外販売が主軸となり、今もそのターンが続いている状態です。とはいえ、そろそろ海外販売だけで大丈夫かという感じになりつつありますけれど。
――川瀬さんの目からみた25年間の変化をコンパクトに話していただきありがとうございます。たしかに今は配信と海外販売のことがよく話題になりますね。
川瀬:それとは別に、最初の話にもでたアニメがメインカルチャーになったのはどこのタイミングだったのかなというのは、今日逆にお聞きしたいと思っていたんですよ。僕はやっぱり「君の名は。」ぐらいから潮目が変わってきた印象があるんです。
ティーン層やF1層にもアニメ的なキャラクターに抵抗がなくなってきて、その親世代もアニメに嗜んできた世代であるという下地があったところに、エポックな「君の名は。」というメガヒット作品がでてきたことで、アニメファンのモノだけだったアニメというジャンルが一般的に受け入れられる空気、アニメ見てますと言える空気があの時期から芸能人もふくめて普通に言うことを憚(はばか)らない空気が生まれたような気がします。そこからはもう「鬼滅の刃」などメガなもののがどんどんでてきた、という状況なのかなと思っています。
それにともなって本来ハイエンドユーザー向けの深夜アニメの一部もメインカルチャーになってきたなというのが、ここ5年ぐらいの実感です。そしてコロナで配信の需要が高まったことで、つねに新しいカタログを更新しないといけない配信業者からはさらにアニメが望まれ、それがやれいくらで売れただの、海外でも売れただのみたいな話が表にでてくるようにもなって、そうなるとアニメは儲かるみたいなことで、またいろいろな方が入ってきて活況を呈しているのが今のアニメ業界だと思います。ただ、これがいつまで続くのか、そろそろ次を考えなければいけないとみんな思いながらも、とりあえず全世界の共通フォーマットである異世界もののアニメをつくっているみたいな状況なんじゃないかと思います。
――今も作品数は増えている印象ですが、2006年にテレビアニメの作品数がめちゃめちゃ多かったのをすごく覚えています。
川瀬:僕もよく覚えています。「灼眼のシャナ」の第1期は05年の10月から06年の3月までオンエアしていたんですけど、その直後の06年春の新番組の本数が81本と聞いて、そこに入らなくてよかったって思ったんですよね(笑)
06年の春番には「涼宮ハルヒの憂鬱」というエポックとなる作品があって、そのクールの話題をさらってしまったのも大きかったです。他にもいくつかスマッシュヒットする作品はありましたが、宣伝の人がいくら頑張っても、ネットでバズるのは「ハルヒ」と「MUSASHI -GUN道-」ばかりで、これは大変だなと思った記憶があります。
――「MUSASHI -GUN道-」、ありましたね。別の意味で話題になったのをよく覚えています。
川瀬:制作した方々の意図とは違ったかたちで目立ってしまったものですから、他の作品が今以上に埋もれてしまっていた感じがありました。僕はそのクールで「女子高生 GIRL'S-HIGH」という作品でプロデュースのお手伝いをしていましたが、この状況で注目してもらうのは本当に難しいなと感じていました。
――「女子高生 GIRL'S-HIGH」、当時楽しく見ていました。ある部分で非常に振り切れていた作品で、こういう言い方をしていか分かりませんが、アニメって映像のクオリティとは別の面白さがあるんだと気づかされて、感銘をうけた思い出があります。
川瀬:ありがとうございます。本編とはまったく別の絵柄で梅津泰臣さんが描いたエンディングもよかったですよね。さすが梅津さんで、ものすごい情念がこもっているな(笑)と思ったのをよく覚えています。
――私自身、そうした06年の盛り上がりのあと、やや盛り下がった状況があったうえで今の活況があることを経験しているため、歴史は繰り返すじゃないですけど、この先はどうなるんだろうと思うときがあります。
川瀬:いや、まったくです。だいぶ話が長くなっていますが、アニメ業界でビジネスという観点から25年お仕事させてもらった僕から見ると、配信で気軽に見られるようになったおかげもあって裾野が広がり、アニメという文化がメインカルチャーになったのはとても良い変化だと思います。ただ、これは僕の勝手な見方でセンチメンタルな思いも含まれているのかもしれませんが、僕らが30代ぐらいのときにつくったり見てきたりしてきたものに比べると、今はとがったアニメが少なくなってきて、全体的におとなしくなってきているように思えてしまうんです。これは、今のアニメが原作通りであることを以前より求められているからとか、いろいろな要因があるのかもしれませんが、もし今のテレビアニメの枠組みでとがったことをするのが難しいのであれば、最初にもお話した別のメディアで面白いことができたらいいのかなとか、いろいろ考えたりするんですよね。
コンテンツの消費の速度が速くなって、30分のアニメを倍速で見ます、TikTokのスピードが体感で気持ちいいという今の若い人たちにどんなコンテンツを届ければ面白いと思ってもらえるのだろうかと考えはじめると、1日中考えられるぐらい楽しいですよ。そこでアニメというジャンルの力をどう生かすか、いろいろなやり方があると思います。あと何年つくれるか分かりませんが、そういう新しい挑戦をちょっとやってみたいなと考えています。
――川瀬さんは、例えば小さな頃に好きだったという理由でアニメ化したいというところではお仕事されていないように思います。今後やりたいことは、具体的なタイトルというより、まったく別の方向性のものをという感じなのでしょうか。
川瀬:この作品をやりたい、関わりたいっていうのもありますよ。実際、2018~19年にやらせていただいた「キャプテン翼」はまさにそれで、子どもの頃にふれた思い入れの強い作品として、どうしてもやりたいなと思っていて、やっと関わることができた作品です。他にも、自分が若い頃に見て面白いと思ったものをどう復活させたら今の人にも面白いと思ってもらえるかななんてこともよく考えます。
昔の作品でも名作には、その根幹にある人間ドラマや面白さには不変なものがあると思っていて、僕はよく「包丁人味平」(作:ビッグ錠)をアニメ化したいって話すんですけれど。
――「包丁人味平」ってアニメ化されてないんですね。
川瀬:なってないです。1970年代の作品ですが、今風にどうカスタマイズしたら成立するんだろう、何かできたらいいなと常々思っています。本当に面白い作品ですから。
――1990年代の漫画「孤独のグルメ」もカスタマイズされてテレビドラマとしてヒットしていますから、根強い人気があるグルメものという意味では面白いかもしれませんね。
川瀬:そうそう。「食戟のソーマ」をやったときに、グルメアニメの面白さって変わらないなと強く思ったんですよね。
――今後の展望として、川瀬さんにとって不変の面白さがある過去の作品のリバイバルにも携わりたいというお気持ちがあるわけですね。
川瀬:そういう企画があったら、ぜひ手助けさせていただきたいなという気持ちはあります。
――今日は長時間ありがとうございました。いろいろお話いただき面白かったです。川瀬さんの直近のお仕事の告知などありましたらお願いします。
川瀬:オープンになっているところで言うと、「終末のワルキューレ」のパート2にプロデュース協力として携わっていまして、7月12日からNetflixで後編の11~15話が独占配信されます。7月番の「七つの魔剣が支配する」にも関わっていまして、10月番の「キャプテン翼 シーズン2 ジュニアユース編」のお手伝いもしている……ぐらいですかね。あとは、何か面白いことをやりたいと思う方がいらしたら気軽に声をかけてくださいっていうぐらいですかね(笑)
――分かりました。川瀬さんにコンタクトをとりたい方がいましたら、カスケードワークス(https://www.cascade-works.com/)まで連絡いただければと思います。最後に、リニューアルしたネットラジオ「のら犬さんのアニメ!ギョーカイ時事放談」(https://norainu-jiji.com/)についても聞かせてください。
川瀬:このラジオがはじまった経緯は飯田(尚史)さんのインタビューで触れてもらっていますが(https://anime.eiga.com/news/117672/2/)、僕のなかでの当初のコンセプトは、売れないプロデューサーの僕と伊平(崇耶)プロデューサーが、業界の偉い人をお呼びしてリスナーと一緒に勉強しようというものだったんですよ。
リニューアルではその原点に立ち返って、フリーになって“リアルのら犬”になった僕がプロデューサーとして食っていくためにどういうことを学べばいいのかということを、ゲストの方にお聞きしていこうと思っています。大きな変化として、声優の浅見春那さんにアシスタントとしてレギュラー出演してもらうことになりました。元相方の里見さんには、ロフトプラスワンでのリアルイベントに引き続き出演してもらっています。
ラジオは2007年から15年以上続いていて、途中変化がありつつも、初期の頃のリスナーの方は、ありがたいことにリアルイベントふくめ、ずっとついてきてくれているんですよ。古参のリスナーの方々は、ここまできたらずっとついてきてくれるだろうと信じているので、今回のリニューアルを機に新しく若い人にも「このラジオ、なんか業界のおっさんがやっているみたいだけど、ちょっと面白いな」みたいに面白がってもらえたらなとも思っています。長く続いた弊害で業界居酒屋度がちょっと強くなってきた自覚もあるので(笑)、本来の姿に立ち返りつつ、もう少し開かれた内容にしていければなと試行錯誤しているところです。よかったらぜひ一度聴いていただけるとうれしいです。
作品情報
タグ
- 灼眼のシャナ
- とある魔術の禁書目録
- SHIROBAKO
- みどりのマキバオー
- ジョジョの奇妙な冒険
- ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか
- selector infected WIXOSS
- 機動戦士ガンダム 水星の魔女
- ストライク・ザ・ブラッド
- 食戟のソーマ
- スターシップ・オペレーターズ
- 神秘の世界エルハザード
- 君の名は。
- MUSASHI -GUN道-
- 女子高生 GIRL'S-HIGH
- キャプテン翼(2018)
- 七つの魔剣が支配する
- キャプテン翼 シーズン2 ジュニアユース編
- 鬼滅の刃
- 涼宮ハルヒの憂鬱(第1期)
- 終末のワルキューレ
- 終末のワルキューレII(前編)
- 終末のワルキューレII(後編)
- 加隈亜衣
- 浅見春那
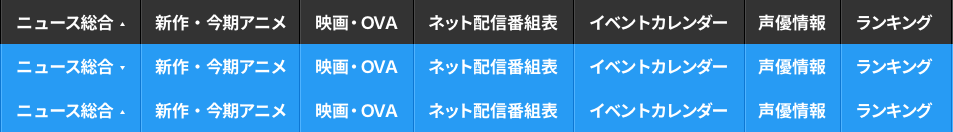
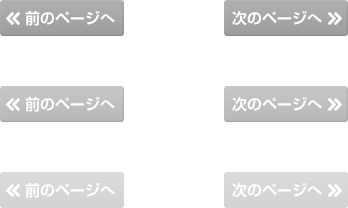








![灼眼のシャナIII-FINAL- 第VIII巻(初回限定版)[DVD]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/nowprinting_dvd.gif)
![灼眼のシャナIII-FINAL- 第VII巻(初回限定版)[Blu-ray/ブルーレイ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51yWtTe8i9L._SL160_.jpg)
![灼眼のシャナII 第I巻〈初回限定版〉[DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51t4v9r5v9L._SL160_.jpg)
![OVA 灼眼のシャナS I[DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51PhxvpPfFL._SL160_.jpg)