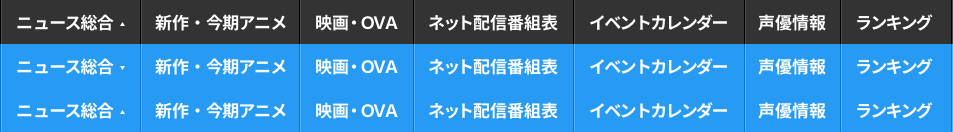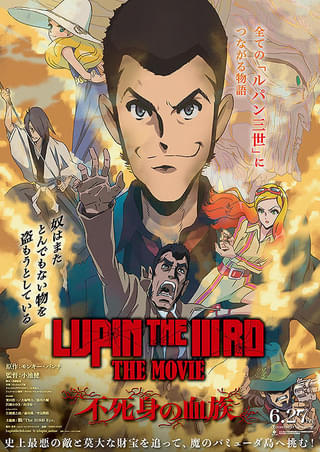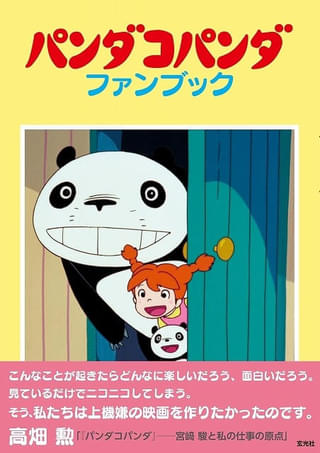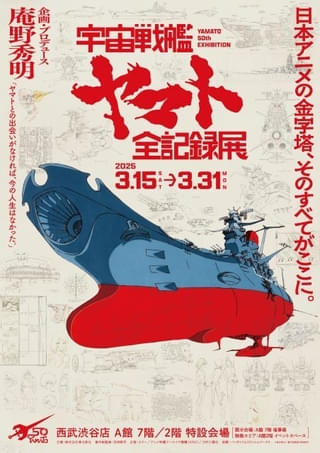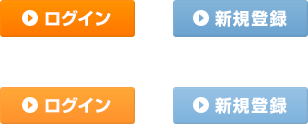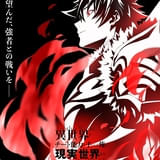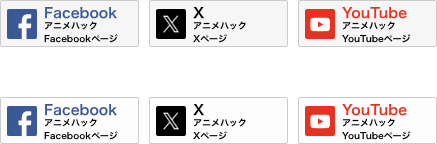![]() 2025年9月13日(土)19:00
2025年9月13日(土)19:00
【氷川竜介の「アニメに歴史あり」】第59回 「勇者ライディーン」の革新性
1975年4月番組の「勇者ライディーン」が50周年を迎えた。この先も続々と70年代のロボットアニメが50周年になるわけだが、中でも「勇者ライディーン」は別格に位置づけられる。「玩具メーカーとアニメクリエイターの共同開発」によるオリジナル作品として後続企画の呼び水となったからである。
今回はそこに至る「合金玩具ブーム」を整理し、「ロボットアニメってこんなもの」ということ含め、「なんとなく誤って共有されている概念」の細部を補正してみたい。
「マジンガーZ」(72)は「玩具販売目的でつくられたロボットアニメ第1号」とされがちだが、広告代理店アサツー ディ・ケイ(70年代は旭通信社)の社史によればそうではない。70年代に入りナショナルクライアントの1社提供が難しくなり、「ミラーマン」(71)ではメインスポンサー大塚製薬は半分の枠のみとなった。さらに後番組の「マジンガーZ」では30秒のCMをバラ売りする必要があり、「とびだすえほん」の万創と玩具メーカーのポピー(バンダイの子会社)が提供した結果、「ジャンボマシンダー」が73年春から夏にかけて大ヒットした。さらに「超合金マジンガーZ」が74年2月に発売されて希代のヒット商品となったが、それは放送開始から1年少々後のことだ。
ポピー自体は1971年に社員7人で創業された小さな企業で、バンダイ本体ではやれないヒモがついて音を出すクラッカーなど〝雑玩〟を担務する予定だった。60年代のバンダイは「サンダーバード」(66)はヒットしたものの、「キャプテンスカーレット」(67)の売上不振でマスコミ玩具(当時の呼称)に慎重だったから、それもポピーに任された。現在、キャラクタービジネスを主導するバンダイのポジションから「マジンガーZに目を付けるのは当然」などと思いこむと、大きく見誤る。
後発としてこの分野に参入したポピーは71年暮れに出した「仮面ライダー変身ベルト」で大ヒットを経験する。高額商品だったが、「光る!回る!」というプレイバリュー(遊んだときの価値)を付けた点が、ブレイクスルーだった。これも放送開始から1年近く経過してからヒット商品となる。そしてポピニカというダイカスト合金のブランドで「サイクロン号」を発売し、72年中はポピニカを続発してマスコミ玩具業界における存在感を増していく。
「マジンガーZ」の玩具参入とヒットも、73年春とされるジャンボマシンダー(60センチサイズの軽量フィギュア)からで、これは「仮面ライダーV3」など特撮ものとの併売であった。74年に放送された「ゲッターロボ」と「グレートマジンガ-」にも超合金玩具は存在するが、当時の雑誌広告を見ると、むしろジャンボマシンダーとポピニカが主力のようにも見える。「ゲッターロボ」は3機のゲットマシンが変形合体して3種のロボットになる画期的なロボットアニメだが、ロボット形態の超合金に変形合体機構はない。アニメーションのメタモルフォーゼ表現を使っていたから再現は無理だったのだ。むしろポピニカで発売されたゲットマシンにささやかな変形機構が装備され、これが玩具のプレイバリューを進化させたと言える。
こうして74年には、ダイカスト合金を用いた玩具「超合金とポピニカ」のブームと進化が着々と進展していった。その手ごたえをもとにポピー所属の工業デザイナー・村上克司が企画時点から参加、「アニメ劇中の活躍と玩具の連携強化」を加味し、ポスト・マジンガーを企図して開発された決定版が「鳥型のゴッドバードに変形可能な勇者ライディーン」というわけだ。変形の映像イメージをほぼ忠実に再現できる、最初の超合金玩具はライディーンから始まったのである。
開発会議には、SF的なメカデザインで知られるスタジオぬえに加え、キャラクターデザイン・作画監督の安彦良和も参加し、かなり長い時間をかけて検討が進められた。「主役メカ」という呼称のとおり、作品内で活躍する「役者」の押し出しは、実際に作画するアニメーターが決める。これもまたエポックメイキングである。安彦自身はその参加を以下のように振りかえっている。
「設定がまた半年がかりで苦労しました。ライディーンが決まらなくて、何回描き直しても〝よくなったね、だけどこうしてよ〟ってなもんで、このぬかるみがいつまで続くのかと思うくらいリテークが出ましたよ」(「マイアニメ 設定資料館第9回 勇者ライディーン」1981年12月号、秋田書店)。
「勇者ライディーン」放送直前まで安彦良和は「宇宙戦艦ヤマト」の絵コンテ、「ゼロテスター 地球を守れ!」のコンテ・演出・作画も担当し、すさまじい仕事量である。結果的にロボットとしての「ライディーン」は、神秘的な設定と美的なラインに神々しい顔だちを兼ねそなえ、女性ファンも熱中する魅力を放つに至った。
「マジンガー」と「ゲッター」は永井豪とダイナミックプロ、漫画家集団によるデザインをアニメ制作会社と玩具メーカーが受けとる「2次展開」であった。ところが「ライディーン」は「玩具とアニメ」が「1次」として玩具ギミック、美観とマルチな魅力を放つことで、新しい価値とビジネススキームを提示したのである。それは73年、74年と2年がかりで「ロボットアニメと玩具の親和性」が着実に進歩し、ビジネス的もに定着したから可能となったことであった。
最初から「ロボット」がメインではなく、「メカ」から段階を踏んでいることも要注意だ。実際、「マジンガーZ」は雑誌社からもテレビ局からも「ロボットものは終わった、古いのではないか」と難色を示されていて、それが往時の社会通念であった。
実際に「テレビまんが玩具のあゆみ」を点検すると、永大、ブルマァクなどポピー以外のメーカーがポピーに先がけてダイカスト合金玩具を先発していて、その題材は「戦闘機」や「戦車」など「非ロボット」を主流としていた。それを牽引したのは「マジンガーZ」の少し前に始まった「科学忍者隊ガッチャマン」のヒットである。73年にこの傾向は実写特撮にもおよぶ。「ウルトラマンタロウ」と「ファイヤーマン」のオープニングが、円谷プロ伝統の「抽象的合成素材とシルエット」から「メカが続々と発進する実写」と激変しているのである。これは玩具のコマーシャル的映像を狙ったとされている。東北新社とポピーとサンライズ(当時は創映社サンライズスタジオ)と「勇者ライディーン」と同じ座組による73年10月番組「ゼロテスター」も、「サンダーバード」の日本版を目指したメカアニメであった。
このメカ中心の潮流が74年には「ロボットアニメと合金玩具」へと一気に転換したというわけだ。その決定版としてオリジナル作品の「勇者ライディーン」が、水面下で開発されていたと考えられる。75年には「ゲッターロボG」、「UFOロボ グレンダイザー」、「鋼鉄ジーグ」と永井豪原作のロボットアニメが続々スタートし、ロボットアニメブームを定着させる。こうして安定化した玩具ビジネス、その大きな市場をめがけて76年に空前のロボットアニメブームが到来することになる。
そのとき量産を加速したのは「オリジナル作品でもビジネスが成立する」という「勇者ライディーン」の実績なのである。やがてオリジナル路線の頂点「機動戦士ガンダム」(79)を生み出す道筋は、このようにして確立されたとも言える。
その全盛期、75年から76年にかけては、SF雑誌で「ロボット・プロレス」という批判も起きた。つまりストーリーを登場人物(あるいは作者側)の工夫や努力ではなく、プロレス(格闘)で解決するのは安易で非論理的だ、という指摘だ。ところがこれに関しても安彦良和が意外な証言をしている。「あんなのはみんなプロレスだ」という見方が、当事者によって否定されているのである。
「あの頃は、ライディーンのような“ロボット・プロレス・アニメ”というのはなかったんです。マジンガーZやゲッターロボがありましたが、あれは素朴に飛び道具を使ったものだったでしょう。オーバーヒートするようなアクションはなかったんです。富野さんが演出でいろいろやって、ライディーンのようなアクションができたのですが、ついていけなかったんですよ。経験者がいなかったんです。それまで3頭身のキャラとか、女の子ばかり描いていた人がいきなり“プロレス”ですから、手探りで描くわけです。こっちも手探りなわけですよ。あんなに苦労した作品はないですね」(「マイアニメ」同)
「ロボット・プロレス」の作画が面倒だったという話は、筆者も直接聞いているし、当然だと思う。たしかに映像では、ライディーンが敵の化石獸に接触して殴りかかったり蹴ったり、牙や角などパーツを掴みかかり、羽交い締めにしたり、投げ飛ばしたりする。さらには寝技に持ちこんで組んずほぐれつするなど、プロレス的な格闘が実に多い。ただし先行作に格闘がどれぐらいあるか無いかはカット数を調べるなど要検証でもあり、数値的に整理分析すれば学術論文が書けるようなテーマもそこに見出せる。
この件は、企画関係者からの証言も別途聞いている。「マジンガーZ」はロケットパンチを発射するとカットを割ってしまうが、「ウルトラマン」は怪獣に近づき首を絞めたり投げ飛ばすので、子どもは後者のほうに興奮するとヒアリングで確かめたという。また子どもの映像視聴体験を観察した親の話を聞くと、ストーリーに関心がない、もしくは理解できなくても「人のかたちをしたもの」が接近して取っ組みあうと、自然と画面にのめり込んでしまうという。闘争から目が離せなくなるのは、おそらく脳に刻まれた本能による反応である。この話は「機動戦士ガンダム」で兵器が人型をしている理由、ミノフスキー粒子の影響で接近戦を余儀なくされる設定のところまで、連綿と繋がっている。
別々に撮ったカットを接着して意味を醸成するモンタージュ技法は、ある程度「映像の記憶」が蓄積された年齢以上でないとうまく作動しないともいう。ワンカット内で絡み合う映像でないと闘争心が喚起されないのかもしれず、「仮面ライダー」のジャンプやキックの切断編集が似た理由で批判されたりもしている。
毎週の放送に作画で対応しなければならないテレビアニメで、2体以上の運動が絡み合う作画を実現するのは酷というものだが、ライディーンを合金玩具とロボットアニメのビジネスを盤石にした重要なファクターとして、深い研究を要するとも考えている。
今回は、「ライディーン」の作品内容を掘り下げるよりも、その「玩具販売」と「映像設計」に話を絞り、重要な歴史的転換点を探った。大学では常々「当たり前を疑え」と教えている。その実例はどこにでもあり、発見の手がかりはいくらでもあるというのが、今回もっとも伝えたかったことである。

氷川竜介の「アニメに歴史あり」
[筆者紹介]
氷川 竜介(ヒカワ リュウスケ) 1958年生まれ。アニメ・特撮研究家。アニメ専門月刊誌創刊前年にデビューして41年。東京工業大学を卒業後、電機系メーカーで通信装置のエンジニアを経て文筆専業に。メディア芸術祭、毎日映画コンクールなどのアニメーション部門で審査委員を歴任。
特集コラム・注目情報
関連記事
イベント情報・チケット情報
- 4月1日(火)
- 2月21日(金)
- 2024年10月31日(木)