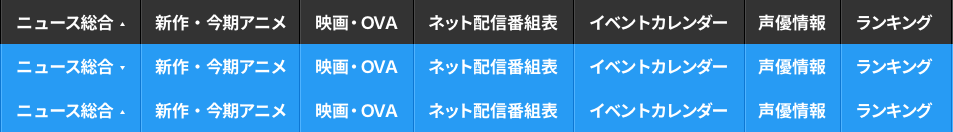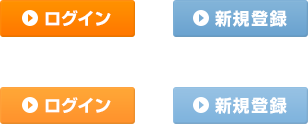![]() 2023年12月30日(土)19:00
2023年12月30日(土)19:00
【氷川竜介の「アニメに歴史あり」】第49回 アニメの描く「物語」の本質が問われた西暦2023年

(C)2023 Ponoc
イメージを拡大
第47回で「アリスとテレスのまぼろし工場」を取りあげたとき述べたように、今年のアニメ映画のタイトルを並べると「なぜこんなにも“物語とは何なのか?”が問われているのだろうか?」という疑問がわく。12月15日公開の「屋根裏のラジャー」(監督・百瀬義行)もそのひとつである。
主人公ラジャーは、少女アマンダが想像で生みだしたイマジナリと呼ばれる少年だ。他人には見えないラジャーが、アマンダと切り離された後、彼女の危機を救うために奮闘する冒険もので、イマジナリを喰らうことで生きながらえる男ミスター・バンティングがヴィランとして登場し、その対立が全編を支えている。
作中では書店、図書館と「物語の宝庫」とイマジナリが強く結びつけられている。物語の触発する想像力とは現実をどのように活性化し、変革しうるものなのか、想像の存在に独立性をあたえることで問いかけてくる。「空想の産物を食い物にしているミスター・バンティング」は、その捕食に際して過剰なまでのグロテスクさを露呈する。
「物語の力」をないがしろにした者が不気味に描かれた点が、非常に引っかかった。商業アニメの紡ぎだす想像力、とりわけ動員を牽引する「物語」は、商取引の材料として生み出される。アニメーションは労働集約産業であり、成立には莫大な費用と時間を要するから自明のことではあるものの、それだけでいいのかという疑問がつきまとう。
作品だったものが「コンテンツ」と呼ばれ始めたのはパッケージビジネスが急成長した1980年代末で、「コンテナの中身」とする点で即物化したのは、そのころからの傾向だ。近年ではもう一歩進んで「IP(Intellectual Property)」と位置付けられ、「知的財産」と訳されている。ネット時代で物理コンテナを必要としなくなった影響もあり、莫大な利益をもたらすことがあるという意味も背後にあるが、意味としては「物語の本質」からさらに遠ざかったように思える。
たしかに「物語」もIPの一部ではある。とは言え、はたしてイコールなのだろうか。決してそうではない。なぜならば「ゆるキャラ」など設定だけで「物語を持たないIP」も存在しているからだ。そして「物語」の役割は金銭取引よりもっと精神的なものである。たまたま現在の「物語取引システム」に金銭が付随しているに過ぎず、手段と目的を取り違えたまま進んでいくのは好ましくないのではないか。
12月8日に公開された「映画 窓ぎわのトットちゃん」(八鍬新之介監督)も、やはり「人の空想力」を重視した点で、この問題意識を喚起する作品であった。原作は黒柳徹子の有名な自伝的小説であるが、アニメ映像化される意味と効果を充分に熟知している。小学生の少女・トットちゃんが内心で抱いている「空想」は美しいものだが、他者と協調性を失った結果、一般の小学校からは放逐されてしまう。新たな学園で居場所を見つけたものの、刻一刻と太平洋戦争と国民の大動員へ向かう世情、医療の甲斐なく喪われる幼い生命など厳しい「現実」と、彼女の空想力が随所で対照されている。
さらに3シークエンスの「夢」がインサートされる。それぞれ独立した画風をもつ作家性の短編アニメーションで、それが現実の事件をクリティカルに照射する役割を有している。ラスト間近、主人公が汽車の中から目撃するものは、冒頭の「日常」につながっていく。現実か空想かあやふやなままの時の音が、確実に現実の「未来」を変えたという描写が、映画全体を「物語を語る物語」としてステージアップさせていると思えた。
こうした「物語を使って物語(の本質)を語る」という形式は「メタフィクション」と呼ばれる。しかしよく知った枠組みに整理しようと解体を始めたとたん、本当に訴求したかった本質がボケるような気もしてくる。もっと切実な「いま損なわれようとしているもの」への異議申し立てが、同時多発的に起きているのではないか。
何が損なわれようとしているのか。たとえばYouTubeでは「短時間で分かる解説動画」が大流行で、アニメもよく対象になっている。流行の「倍速視聴」も「素早く正解を求める目的」に基づくものだし、性急に「正解」を求める若者のニーズに応えるためだろう。アニメ雑誌のインタビュー記事の文字数も、飛躍的に増えて久しい。それは「監督や声優が語った言葉は正解」と認識され、求められるからだという。ストーリー内容的には「ネタバレ」が嫌悪されるのに、「どう解釈するか」は「ネタバレ」、つまり「正解を求める行為」が歓迎される現状は、なんだかイビツに感じられる。
はたして「物語」に「正解」はあるのだろうか。その疑問は、2023年12月16日に放送されたNHKのドキュメンタリー番組「プロフェッショナル 仕事の流儀 ジブリと宮﨑駿の2399日」を視聴した結果、ますます大きくなった。7月14日公開「君たちはどう生きるか」(宮﨑駿監督)のメイキング的な番組である。
綿密な取材の力作なのだが、作中に登場する大伯父を、宮崎駿監督の先輩であり師であり仲間である故・高畑勲がモデルであると「結論ありき」の構成をとっていて、その「正解」へ誘導しようとしている。ポロッと宮崎駿が漏らした言葉を手がかりに、巧みな映像編集によって「高畑への思慕」の数々を接着した結果、あたかもこの新作が、その動機で制作されたような印象を操作するのは、物語の趣旨に沿ったことなのだろうか。
なぜかと言えば、映画「君たちはどう生きるか」とは、題名から自明であるように、「映画が終わった後、物語で何が語られたのか、自分の頭で考え、自分の人生を生きてほしい」という物語だからだ。そこに「正解」があるわけがない。実際に「高畑への思慕」の要素はあったのかもしれないが、制作を進めるうちに忘れられていたのではないか。大伯父は最後のほうであわてて(映画を終わらせるために)再登場させているのだから、それが物語の趣旨であろうはずがない。
同作の制作動機は第47回で触れたように、宮崎駿も帯に推薦文を書いた児童文学「失われたものたちの本」(ジョン・コナリー著、東京創元社刊)にある。母と死別した少年が新しい母になじめず、姿を消した遠い血縁の遺物から「物語の世界」へ旅立つ点で類似性があるし、筆者が注目しているのは序盤部分で亡き母親が語る部分だ。
「物語は、伝わることで命を持つことができるのです。誰かが声に出して読んだり、灯りに浮かび上がった文字を毛布にくるまりながら目で追ったりしない限り、本当の意味でこの世界に生きることができないのです。(中略)誰かが読みだすと、物語は変わりはじめます。人の想像力に根を下ろし、その人を変えてゆくのです。物語は読んでほしがっているのよ、と母親は囁きました。読んでもらわなくちゃいけないの。だから物語は、自分たちの世界から人の世界へとやってくるのよ。私たちに、命を与えてもらいにやってくるの」(田内志文・訳)
これを読んでいる宮崎駿監督が、“物語”を「故人への思慕、追悼」といった「作り手の事情」に閉じこめるわけがない。「物語の使命」が最優先事項のはずだ。物語の機能を研ぎ澄ませ、さらなる共有性を増すために、自己の体験や記憶を材料に使ったのかもしれないが、観客に対しての触媒以上の意味はない。
少なくとも受け止めた側としては、自分の「想像力」にどう作用したかこそが大事なのだ。個々人の読解に際して発生したケミストリーにより「変化した自分の物語」を、さらなる想像力で語ることが要請されていて、題名はその行為を誘導するものである。
どう考えても、ひとつにまとまった「正解」などあり得ない。作り手の事情はガイドにはなっても、最終的な決定事項にはならない。もしそこで思考を停止させたら、「ふーん、君はそんなふうにつまらなく生きるのか」と映画から逆襲されかねない恐ろしさを、「正解を求める人びと」は、どう考えているのだろうか……。
他にもこの問題意識に適合する作品はあるが、ここでは3月24日公開「グリッドマン ユニバース」(雨宮哲監督)を、さらなる考察のヒントとして挙げる。
同作は、テレビ特撮「グリッドマン」とテレビアニメ「SSSS.GRIDMAN」、その続編「SSSS.DYNAZENON」の物語をマルチバース的に扱いつつ、全要素をリミックスした「ユニバース(単一の宇宙)」に融合させるダイナミックな発想の産物である。「SSSS.GRIDMAN」のアニメ世界を創造した後、現実世界に帰還したはずのアカネも再登場する点で、祝祭感あふれるファンムービーの力作であるが、劇中で起きる「奇跡」の根拠としてポロリと「虚構(物語)を信じる人間の力」のことが語られて、驚かされた。
これは世界的ベストセラー「サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福」(ユヴァル・ノア・ハラリ著)に触発されたものと思われる。筆者なりに概括すると、ホモ・サピエンスだけが協力して敵を駆逐して文明を築き繁栄できたのは、虚構・神話・物語を信じ、なおかつ共有できる力を獲得したからだという趣旨で、人類史を再検証した書籍である。そのコンセプトは「失われたものたちの本」とも響き合っているし、そもそも「なぜアニメのペラペラの二次元に描かれた人物が語ることや、死を厭わず行動して起こす奇跡を観客は信じることができるのか」という根源的な疑問を説明可能とする。
これを考え合わせると、やはり「物語」を「正解のあるもの」として矮小化する行為は、可能性を封じこめる点で、あまりにも早計と言わざるを得ない。
では、なぜこの時期に「物語再考」が必要とされるのであろうか。それはこの文脈で語られる「奇跡」を神話的に描くことが「アニメの物語」が有する使命のひとつであるからだ。この「奇跡」を自分なりにブレイクダウンすると、「世界に偏在する残酷な理不尽さ、それがもたらす不可能性の克服」という定義になる。何によって克服するかと言えば、「想像力を自分とは異なる他者に向けること」である。
「君たちはどう生きるか」もまた、そのひとつであった。「正解」として煎じ詰めれば「苦手だと思っていた他者を“お母さん”“友だち”と呼び、認められるようになるまでのお話」だ。こうまとめてしまうと実につまらない。しかし映画に散りばめられた「歯ごたえのある材料」を噛み砕くことで、観客自身の「不可能性」を何とか克服できる力が獲得できるように作られている。実に「いま必要とされる物語」であると思った。
この「不可能性」の中には、個人ではどうすることもできない「疫病」や「戦争」も含まれている。子どものころから、その「巨視的な不可能性」を所与の環境として成長していく人びとには、どんな物語が必要とされるのか。そもそも「物語」自身は何もので、どんな役割や効能をもつものなのか。再点検の時期が来たから、同時多発的にこんな映画が出てきたのではないか。
そんなことを深く考えさせられた2023年であった(敬称略)。

氷川竜介の「アニメに歴史あり」
[筆者紹介]
氷川 竜介(ヒカワ リュウスケ) 1958年生まれ。アニメ・特撮研究家。アニメ専門月刊誌創刊前年にデビューして41年。東京工業大学を卒業後、電機系メーカーで通信装置のエンジニアを経て文筆専業に。メディア芸術祭、毎日映画コンクールなどのアニメーション部門で審査委員を歴任。
作品情報

-
突然起こった製鉄所の爆発事故により全ての出口を失い、時まで止まってしまった町で暮らす中学三年生の正宗。いつか元に戻れるように、住人たちは変化を禁じられ鬱屈した日々を過ごす中、謎めいた同級生の睦実...
-

【Amazon.co.jp限定】『アリスとテレスのまぼろし工場』オリジナルサウンドトラック(CD)(外付け特典:メガジャケ+CDジャケットサイズ・ステッカー)
2023年09月13日¥3,080

-

アリスとテレスのまぼろし工場 (角川文庫)
2023年06月13日¥748

-

【Amazon.co.jp限定】心音(しんおん)※映画「アリスとテレスのまぼろし工場」主題歌(CD)(外付け特典:メガジャケ+CDジャケットサイズ・ステッカー)
2023年09月13日¥1,320

-

アリスとテレスのまぼろし工場 公式美術画集
2024年04月13日¥3,960

特集コラム・注目情報
関連記事
イベント情報・チケット情報
- 2023年10月27日(金)
- 2023年9月16日(土)
- 2023年9月16日(土)
- 2023年9月4日(月)
- 2023年4月23日(日)