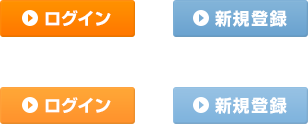![]() 2024年2月23日(金)19:00
2024年2月23日(金)19:00
【氷川竜介の「アニメに歴史あり」】第50回 プログラムピクチャーが生み出す作家性

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2001
イメージを拡大
東京国際映画祭でプログラミングアドバイザーをやっていた時期(2014年から19年)、アニメ作家のレトロスペクティブ(回顧)企画を担当した。作家にフォーカスし、フィルモグラフィ上の重要作品を集中上映し、トークやティーチインを加えて全体を組み立てる手法だ。
映画祭だから、そこでは「アニメを映画にすること」を意識した。アニメーションの原初的な運動性、その驚きと喜びに耽溺することなく、実写映画と同じ地平が目指せないものか。トーキング・アニマルが歌って踊るチャイルディッシュな仕立てからどう脱し、映画的リアリティを獲得するか。観客の心に新たな体験を刻み込めるのか。その試行と錬磨で日本のアニメは進化してきた。その筆者の考え方を海外へ発信したいという想いもあった。
16年からは細田守、原恵一、湯浅政明と作家の特集上映を続けたが、「アニメ作家」と呼ぶべき存在が、思っていたより少ないことも結果的に見えてきた。複数の評価された作品を擁するだけでなく、新作を発表し、映画祭がお披露目や周知になれる監督となると、さらに限られる。新海誠監督は別枠で特集上映があるなどの諸事情もあって、これはかなり狭いものなのだと思い知らされたのだ。
近年、アニメが「IP」の一環として扱われている。これはアニメ監督の作家意識に影響して、新たな作家が出にくくなっているかもしれない。ことに「原作もの」だと作家性を発動させず、いかにクライアント(IPホルダー)の要求を満たしつつ、職人気質のクリエイターたちをまとめて現場を維持するかを、監督が重視していたりする。工事の現場監督のように「前に出て目立ってはいけない意識」が若手にあれば、新たなアニメ作家も出にくくなって当然であろう。
そもそもの話をすれば、アニメ監督とは作家として良いものなのだろうか。そんな根源的な疑問の中から、1950年代、60年代の日本映画黄金時代を特徴づけるキーワード「プログラムピクチャー」が思索の補助線として浮上した。先述のアニメ監督3人には、「プログラムピクチャーが生んだアニメ作家」という共通性があることに気づいたのだ。
細田守監督が注目されたのは、東映アニメフェアの中の「劇場版デジモンアドベンチャー」(99)、「劇場版デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!」(00)である。原恵一監督は、「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲」(01)と「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ!戦国大合戦」(02)、湯浅政明監督も劇場1作目の「クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王」(93)の設定デザインと原画で自由闊達な特徴が大きく注目され、初期劇場作品を彩っている。
つまり「安定的に続く環境という、先鋭的な作家性とは真逆のところから突出する作家性」が、アニメ史では重要ではないかと、改めて気づかされたのである。
ここで日本映画黄金期における「プログラムピクチャー」の成り立ちを確認しておこう。テレビ時代がカラー全盛期に推移するまで、つまり60年代以前は観客がコンスタントに劇場へ足を運んでいた。製作・制作・配給がガッチリ連携し、定常的に「客を逃がさないこと」を続け、上映館をチェーン化するなどの手法で「映画館通いの習慣化」に心血を注いだ。各社競争の中で週間、隔週単位で作品を入れ換え、2本立てなどの策で絶やさず劇場の収入源となる映画作品を供給し続けたのだ。
こうしてブロックブッキングと呼ばれるシステムが定着し、まず年間番組数を決めてからそれを埋めるために映画が量産される。その「上映枠ありき」の作品群が、「プログラムピクチャー」と呼ばれるものだ。「B級映画」も近い概念だが、これは予算枠に起因する呼称なので、ここではリンクしない。
作品がコンテンツだとすると、コンテナ(映画館)が先行して決められているわけだ。そこに注目すべき本質がある。映画会社は要求に応え「一定期間で必ず作品を届けること」を持続する。結果、映画各社にあった「工場」としてのスタジオシステムには、各部門に名匠のような職人が誕生した。ゆえに「プログラムピクチャー」の監督は作家の意識を隠蔽し、職人に徹して職人を指揮していた。しかし、量産システムの中で「監督デビュー」のチャンスは増加し、野心を秘めた監督が今でも「作家」として名を残しているのは、周知の事実である。
細田守、原恵一、湯浅政明らを「アニメのプログラムピクチャー出身者」と位置づけると、そこに相似性が見えてくる。これは、「東京国際映画祭2019」で上映した「海獣の子供」の渡辺歩監督が「映画ドラえもん」シリーズ出身である事実を加えると、より鮮明となってくる。
では、どのようにして「アニメのプログラムピクチャー」が誕生したのだろうか。
「プログラムピクチャー全盛期」の60年代に、「テレビまんが混載興行」が誕生したことが始まりである。ゴールデンウィーク、夏休み、冬休み、春休みと学校の長期休暇に合わせ、親子連れを動員する企画で、「季節商品」と呼べる安定性がある。ここで言う「テレビまんが」は「アニメ」「特撮」「人形劇」を区別しない概念のことだ。
その混載興行は、まるで漫画雑誌のようなキャラクターを多数配したポスターで児童を誘い、「東映まんがまつり」「東宝チャンピオンまつり」の二大勢力となって一時代を築く。それはテレビ時代と連動した日本映画の斜陽期と重なる。だから、東映動画(現:東映アニメーション)が始めた長篇漫画映画も、東宝のゴジラ映画も単独企画(2本立て興行)が維持できなくなり、テレビまんがのブローアップ(拡大版・もしくは新作短編)を多数ラインナップした混載プログラムの中で延命策をとっていたわけだ。
ところが「東宝チャンピオンまつり」は、ブローアップできるテレビ新作を常時量産する東映に先がけて終わっていく。きっかけは、1980年に「映画ドラえもん のび太の恐竜」が公開されたことにある。実はこのとき、「モスラ対ゴジラ」(1963年の映画をリバイバル公開)が併映作品にされた。おそらく関係者側は「ドラえもん映画」が当たるとは思っていなかったのだろう。第3次怪獣ブームだったこともあり、ゴジラ映画を付け、人気漫画家・松本零士によるポスターを新作して宣伝することで、保険をかけたのだ。「チャンピオンまつり」に近い発想があり、そのフェードアウトとみることもできる。
これは破格のヒットとなる。これは「のび太の恐竜」が「映画としての条件と風格」を備えていたことが大きい。テレビの短い尺では不可能なスリルとサスペンス満載の冒険ものの体裁で、始まりと終わりがあり、永遠の別れが描かれ、のび太の成長が核にある。それが「映画の条件」である。テレビのルーチンに必要な所与の条件も映画向けに補強され、ジャイアンは頼もしいパワータイプ、スネ夫は頭脳タイプと助力する友人の役割も変わっている。筆者は映画の本質を、現実を変容させるある種の「異世界体験」と認識しているから、「テレビアニメの異世界転生効果」もあったと認識している。
こうして翌年から藤子・F・不二雄が「大長編ドラえもん」をコロコロコミックで描きおろし、それを新作映画として毎年3月に公開される「定番興行」が確立した。今年も第43作「映画ドラえもん のび太の地球交響曲」が3月1日に公開される。
以後は文字数の関係で圧縮するが、「映画 それいけ!アンパンマン」シリーズが89年開始(6~7月)、「映画クレヨンしんちゃん」シリーズが93年開始(4月公開)、「劇場版名探偵コナン」シリーズが97年開始(4月公開)、「ポケモン・ザ・ムービー」シリーズが98年開始(7月公開で2020年冬に中断)と、東宝系で学校の長期休暇に合わせた「定番興行」が続く。それは「ドラえもん」の成功が開拓したものなのだ。
その20億から30億円規模のコンスタントな興行収入は、シネコン時代以後に増大したスクリーン数の安定的な維持に貢献したはずだ。さらに近年ではこの数字が大きく跳ね上がっている。23年4月公開の「名探偵コナン 黒鉄の魚影」が興行収入138.8億円をマークした。立川譲監督が並行して作家性の強い「BLUE GIANT」を同年2月に発表していることは、ここで扱っている「プログラムピクチャーと作家性」を考える事例として最適であろう。だから、引き続き考えていきたいテーマなのだ。
なお、当事者はどう考えているのだろうか。細田守監督が東映アニメーションを辞職し、「時をかける少女」(06)を発表して作家として改めて注目が集まり始めた時期、筆者が取材したロングインタビューからヒントが得られたことがある。原恵一監督からも、類似のヒントをいただいた。それに筆者のメーカー勤務経験を加味して考察した解釈を以下に示す(当事者の発言ではない)。
プログラムピクチャー的な作り方は、短期決戦であるがゆえに与えられるリソースも時間も限られていて、過酷だ。その分、知恵やチームワークを駆使して乗りきることになるが、過酷な分だけ「せめて面白くしないとやってられない」という気持ちが忍び込んでくる。これは「決められたとおりに作りなさい」という上層部の期待と、コンフリクトを起こす。当然のことだ(実際、事後に怒られたりするらしい)。
クリエイションの集中度が上がったがゆえの切迫した温度上昇が加わることで、制作現場も「今度は違うことをやってるぞ」と高揚感を共有する。そのスタッフ同士のケミストリーが、「上位の面白さ」を招来する。その結果、「プログラムピクチャー」として油断していた観客の心にも、深く作用して前代未聞の感動を呼ぶことになる。
この「相互作用全体のプロセス」が「作家性」として認識される、ということではないのか。しかも、いったんその「扉」を開いてしまった作り手は、後戻りができなくなる可能性も大だ……。
こうした構造的な分析は、「日本アニメの進化」を考えるとき、非常に重要だと考えている。なぜならば、この考察における「プログラムピクチャー」を「玩具販売目的のロボットアニメ」に置き換えてみると、「機動戦士ガンダム」で起きたことの相似形が発見できるからだ。他にもまだまだ相似する事例はいくらでもあるだろう。
アニメの場合の「作家性」を「個人の内面から湧き出てくるもの」と「属人性」のみに引き寄せた文芸的な読解には、その直線性による限界があるのではないか。筆者はそう繰りかえし主張してきた。もっと大きな構造分析を加え、因果関係を連立方程式のように解いて、ネットワークを可視化しなければならないのではないか。分析の機会があるごとに、この考え方は確信に近づくばかりである。

氷川竜介の「アニメに歴史あり」
[筆者紹介]
氷川 竜介(ヒカワ リュウスケ) 1958年生まれ。アニメ・特撮研究家。アニメ専門月刊誌創刊前年にデビューして41年。東京工業大学を卒業後、電機系メーカーで通信装置のエンジニアを経て文筆専業に。メディア芸術祭、毎日映画コンクールなどのアニメーション部門で審査委員を歴任。
タグ
特集コラム・注目情報
関連記事
イベント情報・チケット情報
- 8月11日(日)
- 8月11日(日)
- 6月8日(土)
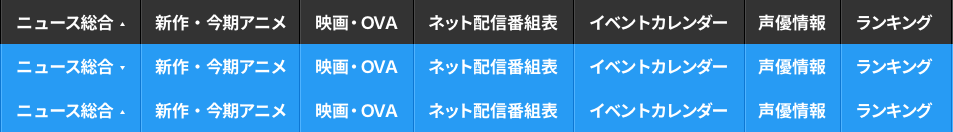


![映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61E24GRXSDL._SL160_.jpg)